発刊物の紹介と購入 |
| 読谷村史第三巻 資料編2 文献にみる読谷山 目次 |
| 口絵 発刊のことば 読谷村長 山内徳信 村史発刊によせて 読谷村史編集委員会委員長 新崎盛繁 目次 凡例 まえがき 本書をお読みになる村民の皆さんへ 一 歴史は、魂の拠り所、未来への羅針盤 (一)歴史は我々人間の誇りである (二)歴史に魂の拠り所を求める (三)明日のための歴史 (四)歴史を伝える情熱 二 この本「文献にみる読谷山」の読み方 (一)沖縄史を区切ってみると(時代区分) (二)沖縄史を飾る読谷山の歴史 (三)この本を作った目的 (四)想像と情をこめて これがこの本の読み方です (五)この本には、たとえばこんなおもしろい記事が載っています |
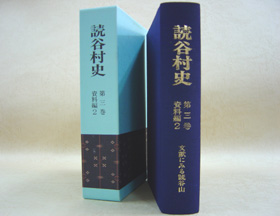 |
| 第一章 『おもろさうし』にみる「よんたむさ」 一 おもろ概説 (一)『おもろさうし』について (二)『おもろさうし』の出来た年代について (三)「おもろ」とは何か (四)「おもろ」の語源 (五)「ぶし名」について (六)読谷山関係の「おもろ」について 文の解説 1 てやんおなちやらのふし 巻九ノ三二 2 うちいてはさはしきよかふし 巻十ノ四四 3 あかつめつらしやかふし 巻十三ノ六六 4 あかつめつらしやかふし 巻十三ノ六七 5 あおりやへかふし 巻十三ノ六八 6 しよりえとのふし 巻十三ノ六九 7 しよりえとのふし 巻十三ノ一五七 8 しよりえとのふし 巻十三ノ一五九 9 しよりえとのふし 巻十三ノ一六○ 10 しよりえとのふし 巻十三ノ一六一 11 しよりえとのふし 巻十三ノ二〇四 12 (ぶし名無し) 巻十四ノ五七 13 (ぶし名無し) 巻十四ノ五八 14 (ぶし名無し) 巻十四ノ五九 15 大さとのけすのおもいあちのふし 巻十五ノ六二 16 あおりやへかふし 巻十五ノ六五 17 ふるけものろのふし 巻十五ノ六六 18 ふるけものろのふし 巻十五ノ六七 19 ふるけものろのふし 巻十五ノ六八 20 やなのよ・きよらかふし 巻十五ノ六九 21 ひるのやしゑのしかふし 巻十五ノ七〇 22 ひるのやしゑのしかふし 巻十五ノ七一 23 へとのおやのろかふし 巻十五ノ七二 24 大にしのたらつかふし 巻十五ノ七三 25 大にしのたらつかふし 巻十五ノ七四 26 ちやうおやおゑまのしかふし 巻十五ノ七五 三 おもろに見る「あかいんこ」 (一) あかいんこについて (二) あかいんこ関係おもろ (三) あかいんこの名 (四) 吟遊の足あと (五) あかいんこはサンシンの始祖か (六) あかいんこの所業 (七) とひやくさす ちよわれ(いついつまでも) 第二章 「王府正史」にみる読谷山 一 全体解説 二 『中山世鑑』に載った読谷山 (一) 読谷山王子 1 首巻(先国王尚円以来世系図) (二) 読谷山按司 1 巻三「永楽二十年壬寅尚巴志御即位」の項 三 『中山世譜』に載った読谷山 (一) 読谷山 1 首巻「三府五州三十五郡」の項 2 巻三「玉城王」の項 3 巻九「尚敬三」の (二) 泰期 1 巻三「察度王」の項 (三) 読谷山按司 1 巻四「尚思紹王」の項 (四) 阿普尼是 1 巻四「尚巴志王」の項 (五)読谷山王子 1 巻七「尚清王」の項 2 巻九「尚益王」の項 3 巻九「尚敬三」の項 4 巻九「尚敬三」の項 5 巻十「尚穆王」の項 (六)読谷山親方 1 巻七「尚寧王」の項 2 巻十「尚成王」の項 (七) 座喜味親方 1 巻九「尚敬三」の項 2 巻十一「尚瀬王」の項 3 巻十二「尚育王」の項 四 『中山世譜附巻』に載った読谷山 (一) 読谷山 1 附巻之三「尚益王」の項 (二) 渡慶次 1 附巻之一「尚豊王」の項 (三) 読谷山王子 1 附巻之四「尚穆王」の項 2 附巻之五「尚瀕王」の項 (四) 読谷山按司 1 附巻之一「尚寧王」の項 2 附巻之一「尚豊王」の項 3 附巻之一「尚賢王」の項 4 附巻之二「尚貞王」の項 (五) 読谷山親方 1 附巻之一「尚寧王」の項 2 附巻之一「尚豊王」の項 (六) 座喜味親方 1 附巻之一「尚豊王」の項 2 附巻之二「尚貞王」の項 3 附巻之三「尚敬三」の項 4 巻之四「尚穆王」の項 5 附巻之五「尚瀕王」の項 6 附巻之六「尚育王」の項 (七) 喜名親方 1 附巻之四「尚穆王」の項 2 附巻之五「尚?王」の項 (八) 渡慶次親方 1 附巻之四「尚穆王」の項 (九) 禰覇親方 1 附巻之四「尚穆王」の項 (十) 高志保親方 1 附巻之七「尚泰王」の項 五 『琉球国由来記』の中の読谷山 1 官爵位階職之事 2 無手今官職御蔵之事 3 諸間切諸島失地頭紋理ヲエカ人之事 4 〔事始 乾〕天地門 5 首里中火神並御嶽之事 6 名処祭祀 7 年中祭祀 六 『琉球国旧記』の中の読谷山 1 〔官職部〕取納奉行 2 〔関梁〕庇謝橋 3 〔神殿〕読谷山郡 4 〔山川 嶽 森 威部〕読谷山郡 5 〔泉井〕読谷山郡 6 〔江・港〕読谷山郡 7 〔火神〕読谷山郡 8 〔郡邑〕読谷山郡(領邑十六座) 9 〔郡邑長〕読谷山郡 10 駅 七 『球場』『遺老説伝」にみる読谷山関係記事 1 附 国分れて三と為る。(玉城王元一三一四年) 2 二十三年、明の太祖、使を遣はして招撫す。王、始めて投誠納款し、以て中国に通ず。(察度王二十三・一三七二年) 3 二十八年、弟、泰期等を遣はし、元旦を表賀す。(察度王二十八・一三七七年) 4 三十三年、太祖、尚佩監奉御路謙に命じて、貢使春期等を護送して国に至らしむ。(察度王三十三・一三八二年) 5 五年、阿摩和利、護佐丸を讒害す。(尚泰久正三・一四五八年) 6 二年、葛葉萎に文子を授く。(尚豊正二・一六二二年) 7 始めて恩納・大宜味・小禄・久志等の四郡を置く。(尚貞三五・一六七三年) 8 座喜味村の上地、しばしば餓ひょうを済ひて、座敷位及び御掛物一幅を褒賜さる。(尚敬三元・一七一三年 9 始めて士臣を直擢して諸浦の在番を授くるを定む。(尚敬三十一・一七一三年) 10 鶴雁来遊す。(尚敬三十四・一七二六年) 11 取納奉行と改名す。(尚敬王十六・一七二八年) 12 首里の翁欽忠等、庇謝橋を改修す。(尚敬三十七・一七二九年) 13 各処横目の員数を改定し、在番を輪投す。(尚敬王十九・一七三一年) 14 水蔵を読谷山の駅宅に創造す。(尚敬王一一十一・一七三三年) 15 二十三年、法司蔡温に命じて、始めて官僚に山林の法を教へしむ。(尚敬正二十三・一七三五年) 16 読谷山郡瀬名波邑を、久良美知屋原に移立す。(尚敬正二十五・一七三七年) 17 読谷山間切座喜味村の照屋の妻比奈、早く寡し、家貧なるも節を守りて嫁せず、勤倹子を養ひて以て家を興す。 (尚敬王三十二・一七四四年) 18 読谷山郡百歳の老人に爵位・物件を賜ふ。(尚穆王二・一七五三年) 19 五月朔日、読谷山郡瀬名波村を高志原に遷すを推す。(尚穆王十五・一七六六年) 20 九月十七日、主上北巡して山を省る(俗に杣山御見分と呼ぶ)。(尚穆王二十七・一七七八年) 21 四月十四日申時、読谷山郡喜名村に、忽ち竜、風を起して、人家五十五軒を損壊し、村を囲む松木六株・唐竹千余株を吹倒す。(尚穆王三十一・一七八二年) 22 三月二十八日、渡名喜島の宮平仁屋の善行を褒奨す。(尚穆王三十二・一七八三年) 23 国中及び各外島人民の米銭を奉借するを褒賞す。(尚穆王三十六・一七八七年) 24 四十二年癸丑正月十一日、読谷山郡に下知役一人を設建することを推す。(尚穆王四十二・一七九三年) 25 本年六月初十日、雷、渡具知洋面に震ふ。(尚□三十三・一八一六年) 26 本年、読谷山郡渡具知村の池原筑豊之等の功を褒嘉して各々爵位を賜ふ。(尚□王二十七・一八三〇年) 27 本年、呉維興瀬名波親雲上宗愛の善行を褒嘉して中布を賞賜す。(尚 王二十七・一八三〇年) 28 本年正月、菩薩一位の読谷山郡渡具知港に流来する有り。即ち之れを授けて上天后宮に奉安す。(尚育王五・一八三九年) 29 本年四月十四日酉未刻、阿蘭陀船一隻の飄来する有り。(尚育王八・一八四二年) 30 本年、那覇西村の魚氏先の許田筑豊之親雲上音本の妻の忠志を褒嘉して世々譜代籍に陞す。(尚泰三五・一八五二年) 31 本年十二月、読谷山郡上地村を旧籍に遷すことを催す。(尚泰三十一・一八五八年) 32 本年、読谷山郡宇座村の山川筑豊之を褒嘉して爵位を賞賜す。(尚泰三十三・一八六〇年) 33 本年、読谷山郡波平村の土民二名・宇座村の土民三名・高志保村の土民二名・喜名村の土民三名・長浜村の土民二名・渡慶次村の土民三名・儀間村の土民二名を褒嘉して各爵位を賜ふ。一尚泰三十五・一八六二年) 34 本年四月二十五日、雷、崎山村の人家及び雨乞壇・読谷山郡字座村等の処に震ふ。(尚泰王十六・一八六三年) 35 十七年甲子、唐栄孫氏安座間通事親雲上克槙の母・読谷山郡喜名村与那覇筑登之両人の長命を賞して、賜ふに物件爵位を以てす。(尚泰王十七・一八六四年) 36 本年、壷屋村の高江洲筑登之親雲上を褒嘉して新家譜を賞賜す。(尚泰王十八・一八六五年) 37 本年、読谷山郡に有る所の比謝矼、着令して矼二座を加設し、以て修造を為さしむ。(尚泰王二十・一八六七年) 38 附 読谷山郡比謝村の儀間、右京の号を得。(尚貞三四十一・一七〇九年) 39 岩穴にあった二つの鏡 |
第三章「近世史料」にみる読谷山 |