<-前頁 次頁->
日本軍政下のフィリピン
フィリピン民衆と抗日ゲリラ
在フィリピンアメリカ軍が撤退し、日本軍がフィリピンを支配するようになると、日本人移民と現地の人々の力関係は逆転することになる。夜間外出禁止令、建築物の接収、フィリピン全国の新聞雑誌書籍の発行所および印刷所の接収・統合、映画館の統制、公共の場でのアメリカ国旗の掲揚及び国歌の演奏の禁止、町・橋・川・公園の名前を日本風に改名、教育の基本原則の発令、カトリック教会の統制、軍票の流通など、日本軍は、フィリピンに対する政策を次々と実行して、フィリピン社会はたちまち日本軍の支配下に組み込まれていった

。フィリピン人歴史学者レナト・コンスタンティーノとレティシア・R・コンスタンティーノは、日本軍によるこれら一連の政策を「新植民地主義」と呼んでいる。
多くのフィリピン人は日本軍のこのような政策と行為をどのように受け止めていたのだろうか。オランダの東南アジア近現代史家のヤン・M・ブルヴィーアは、「行政機関のフィリピン化という日本の政策と外面的な独立の許容が、いかなる感銘も与えなかったのは、民族意識が刺激をまったく必要としていなかったフィリピンの場合だけだった」と述べ、その理由は、「この国はすでにフィリピン人自身によって支配されていたので、ほとんどいかなる本質的な変革も行なわれなかった」ことと、「日本の保護下での独立も、戦前のコモンウェルス憲法下の状況を少しも改善するものではなかった」からだと述べている

。レナト・コンスタンティーノとレティシア・R・コンスタンティーノも同様のことを述べている。「フィリピン人がほぼこぞって日本人に示した敵意と、アメリカ人に示した深い忠誠心とは、他の被侵略諸国でおこった反応とはまったく一致しない。なぜなら、自分を西欧植民地主義者と一体化してみようとはしなかった他のアジア諸民族とはちがって、フィリピン人はアメリカの巧妙な支配技術にすでに屈服していたからである」

。これらの指摘は、日本の「大東亜共栄圏」や「八紘一宇」というスローガンがフィリピンに与える影響力が弱かったことを意味する。さらに、日本軍や日本人移民が根強い敵対心にさらされたことを示唆している。
実際、日本軍政下のフィリピンでは、多くの抗日ゲリラが組織された。その数は一三〇〇団体という説(アメリカ軍情報)や、一〇〇団体、 二七万人という説がある

。これらのうちの多くが、マッカーサー率いるアメリカ軍と統合されていたフィリピン軍の将校たちが地下に潜伏した後に組織されたものであり、彼らの重要な役割は、オーストラリアに撤退したアメリカ軍に情報を提供することであった。例えば、マッカーサーはゲリラ組織のリーダー、ペラルタ宛てに次のような電信指令を送っている。
「何よりも重要な使命は、貴下の組織の保善であり、最大限に情報を入手することである。ゲリラ活動は、当方が再度指令を与えるまで延期されたい」

。
このような抗日ゲリラが多く存在した中で、中部ルソン島で組織されたフクバラハップ(人民抗日軍)は、政治目標、組織のあり方など、他の多くのゲリラ組織とは質の異なるものであった。フクバラハップを支えていたのは、「共産党、社会党、急進的農民や労働組合活動家たち」であり、「反帝国主義の立場」からフィリピンの「独立と民主主義」を公式の目標として宣言していた

。フクバラハップは、一〇〇人単位の中隊に組織され、中隊は小隊、分隊に分れており、組織的な軍隊であったが

、住民の自治組織形成にも影響力をもっていた。例えば、「フク団支配下のバリオ住民は、自治への直接参加が許されるようになって、自分たちの地下組織に誇りを抱くようになった」

。フクバラハップは、ルソン島中部を中心に多くの民衆に支えられていたのである。
日本軍政下の日本人移民
拘束されていた日本人移民が自分たちの耕地に帰ると、多くの者が軍属となり、また各地で義勇隊が結成された。義勇隊員は銃をもって武装した。義勇隊員となった松田※※(当時二十一歳、喜名)は、食料調査を命じられた。実際は、フィリピン人からトウモロコシを「徴発」することが仕事であったという。
当時三十三歳だった知花※※(波平)は、日本軍の空襲の後すぐにフィリピン人によって学校に収容された。フィリピン人の小さな子どもに石を投げられたこともあったという。収容先の学校の教室では、八〇人から九〇人ほどで生活した。食事は一日二食で粗末なものだった。校舎にはフィリピン人の監視がおり、闇で日本人にパンを売っていた。日本人に暴力をふるうフィリピン人もいた。そのような収容所生活が一〇日ほど続いた後、日本軍がやってきて、彼女たちは解放された。今度は、日本人がフィリピン人監視員たちを蹴ったり殴ったりしたという。立場が逆転したわけである。移民たちが収容されている間に暴力を振るったフィリピン人の犯人探しがはじまり、射殺されたフィリピン人も少なくなかった。
このような暴力は、日本軍によって組織的に行われたこともあった。知花※※(長浜)によると、日本軍の上陸後、ミンタルの女学校や寺に日本兵が駐屯するようになった。日本人は家に戻り、それぞれの生活をはじめた。そのような時に、ミンタル駐屯の日本兵がフィリピン人を殺していた。昼間は寺のお堂に閉じ込めておいて、夜になると裏山へ連れていって銃殺した。職場の寮で「今日は何人殺したらしい」という話をよく聞いたという。
また、軍隊だけでなく移民によるフィリピン人への暴力も行なわれた。読谷山村出身のTは、次のような経験をしている。
「私は農業をして家族を支えて暮らすために、出稼ぎ移民したわけだが、戦争に関して特別な体験をした。日本軍上陸後、現地人と日本人の立場が逆になって、今度は仕返しみたいな感じで、一般の日本人移民が、常日頃からトラブルのあったフィリピン人を連れて行ってね。日本人がフィリピン人を殺す現場も見た。日本人は現地人から土地を借りていたから、フィリピン人地主と日本人の間でトラブルを起こすところも多々あったわけさ。そういう日本人とトラブルのあった地元民を集めてね。私は当時、トラックを持っていたので、何度か彼らを乗せて川まで運ぶ手伝いをした。要するに戦前、フィリピン人にいろいろやられた者が、やり返したわけ。私がトラックで運んだ人達は、川縁に連れて行かれ、そこで日本刀で…。あんなにまでせんでもいいがなと思ったが。仕返しをした人の中にはウチナーンチュはほとんどいなかった」(聞き取り調査)。
このように、多くの日本人移民とフィリピン人の関係は、日本軍政下では全く逆転した。
フィリピン「決戦」
サイパン戦で多くの兵力を失った参謀本部は、一九四四年(昭和十九)七月二十五日「国力の戦力の徹底的重点(七〜八割)を構成して、主敵米の進攻に対し決戦的努力を傾倒し、一部(二〜三割)をもって長期戦的努力を行なう」という戦争指導方針を決め、「捷号(しょうごう)」作戦計画が策定された。具体的には、「フィリピン、台湾および南西諸島、本土(北海道を除く)、北東方面(千島、樺太、北海道)と、敵来攻の可能性の順に決戦場を指定し、それぞれ『捷一号〜捷四号』と名づけた」

。フィリピンを主目標においた捷一号作戦では、陸上決戦場はルソン島に限定して、その他の島へのアメリカ軍の来攻に対しては、陸海航空兵力と海軍艦艇による「決戦」を行なうという計画をたてた。これに基いて、陸軍は第十四方面軍と第三十五軍の再編成と創設、海軍は、第一遊撃部隊、第二遊撃部隊、機動部隊本隊、第一航空艦隊をフィリピンに進出させるべく配置した

。一方、同時期のアメリカ軍では、マッカーサーの強い提案により、フィリピン・レイテを攻略する作戦が承認された

。これによって、フィリピンが戦場となることが決定的となった。
一九四四年(昭和十九)八月、次々と内南洋を占領した後、アメリカ軍は、硫黄島(八月三十一日)、ダバオ [ミンダナオ島](九月九日)、セブ [セブ島]、レガスピー [ルソン島南部]、タクロバン [レイテ島](九月十二日〜十四日)を空襲した。そして、沖縄への空襲(十月十日)と台湾沖航空戦(十月十二日)の後、十月二十日にレイテ島に上陸を開始した。これに対して、日本軍参謀本部は、ルソン島決戦という当初の計画を転換し、レイテ島を決戦場にする作戦を立てた。海軍の主力戦艦、大和や武蔵をもつ第一遊撃部隊第二艦隊(栗田艦隊)を中心とする連合艦隊はレイテ湾に向かった。機動部隊(小沢部隊)は、おとりとなってアメリカ軍を引きつけ、栗田艦隊のレイテ湾突入を容易にするための陽動作戦としてルソン島北部に向かった。さらに、アメリカ軍がレイテ島に上陸した日、マニラの北に駐屯していた部隊では、戦闘機での体当たり攻撃を公式の任務とする「神風特攻隊」が初めて組織された。二四名の神風特攻隊員の任務は、レイテ決戦を目指す連合艦隊を援護する目的であった

。日本軍にとってレイテ決戦の焦点は、戦艦大和や武蔵を率いる栗田艦隊のレイテ湾突入であった。しかし、栗田艦隊は、途中で反転し、結局レイテ湾には進入しなかった。レイテ沖海戦は、アメリカ軍の船舶損害(沈没)が六隻だったのに対し、日本海軍の損害は、主力の一翼を担っていた武蔵を含む三〇隻に達するという日本軍の大敗に終わった

。
 |
| ブルネイ湾に待機する長門・大和・武蔵の戦艦群(昭和19年10月21日)『写真提供 文藝春秋』 |
昭和十九年十二月十八日、大本営陸軍部は、「決戦思想ヨリ持久思想ヘ転換ス」という指示を出し 、十二月十九日、山下第十四方面軍司令官は、鈴木第三十五軍司令官にレイテ作戦終了を通告した。
、十二月十九日、山下第十四方面軍司令官は、鈴木第三十五軍司令官にレイテ作戦終了を通告した。
「第三十五軍司令官は自今、中南部比島において永久に 抗戦を継続し、国軍将来における反抗の支とう(しとう)たるべし」 。
。
この文面から、日本軍の組織的な決戦体制が終わったにもかかわらず、方針がないままに戦闘の継続だけが指示されたことがわかる。
アメリカ軍は、一九四五年(昭和二十)一月三日ミンダナオ島に進出、一月九日ルソン島に上陸、二月三日マニラに進入、三月五日には、日本軍が敗退した 。日本兵や日本人移民たちは山間部への避難を余儀なくされた。その頃、「在留日本人の子どもは作戦上足手まといになるので殺してもよいという命令」が出ていたことや、味方同士で食べ物の奪い合いをするという状況が生じたと城田吉六は述べている
。日本兵や日本人移民たちは山間部への避難を余儀なくされた。その頃、「在留日本人の子どもは作戦上足手まといになるので殺してもよいという命令」が出ていたことや、味方同士で食べ物の奪い合いをするという状況が生じたと城田吉六は述べている 。
。
山間部をさまよう日本兵や移民者たちにとって、自らの命を脅かす者はアメリカ兵やフィリピン人兵だけでなく、山間部に住む少数民族や、また「味方」でもあった。食料不足の状況の中での山中の生活は、敵味方入り乱れた殺し合いの状況を生み出した(知花※※の体験記参照)。
フィリピンにおける読谷山村出身戦没者
読谷村史編集室作成の「読谷村戦没者名簿」によると、フィリピンで戦死した読谷山村出身者は二三一人である。戦時中、何人の読谷山村出身者がフィリピンに在住していたかについての明確な統計はないが、「海外旅券下付表」が参考になる。それによると、戦前(明治四十年〜昭和十六年)のフィリピンへの渡航者全体は六四六人である
〔「移民の行先」参照〕。この数字にはフィリピンで生まれた人々が含まれていないので、戦時中の読谷山村出身者の人口はもっと多かったと推測される。このことを考慮したとしても、六四六人がフィリピンへ渡り、二三一人が亡くなったということは、かなり高い割合で戦死したと言わねばならない。
|
表-2 フィリピンにおける読谷山村出身戦没者

|
図-6 フィリピンにおける読谷山村出身戦没者(昭和20年)
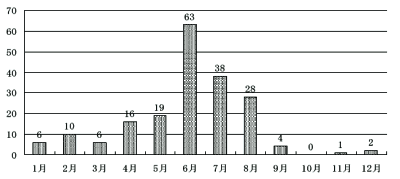
|
読谷山村出身者が亡くなった時期は、昭和二十年に集中しており、その中でも六月に最も多くの人が亡くなっていることが目を引く。六月は、牛島中将が自決して、沖縄戦における日本軍の組織的な戦闘が終わった時期である。その時期に、最も多くの読谷山村出身者がフィリピンで戦死しているのである。フィリピンでは、前年昭和十九年十二月十九日には、連合艦隊の大敗とともにレイテ作戦が終了し、昭和二十年三月にはマニラの日本軍は敗退している
〔フィリピン「決戦」参照〕。昭和二十年四月以降は、日本兵と日本人移民たちが山間部に逃げ込んだ時期である。このことから、四月以降に戦死した人々は、アメリカ軍の攻撃によるものだけとは考え難い。
ダバオのカリナン尋常高等小学校の教員であった新崎※※(比謝矼)は、昭和二十年四月二十九日(天長節)頃、「邦人はジャングルへ逃げろ」という情報に従い、知人の数家族と共に山中の避難小屋で生活をすることになった。当初は、バゴボ族の女性を妻にもつ知人(沖縄出身者)に紹介されたバゴボ族の首長に食料を分け与えてもらっていた。その頃、新崎は、バゴボ族の食料を盗んだ日本兵と争うという経験もした。後になると、さらに山奥へ避難し、猿や猪を捕らえて食した。新崎は、木の根にもたれかかるように死んでいる日本兵や、日本軍が設営したいくつかの小屋の中で白骨化した日本兵をみた。日本兵も移民も山中に追い詰められ、食料不足の中で生きるのがやっとという生活を余儀なくされていた。新崎の山中での生活は、四月から九月までの約六か月間続いた 。
。
山中の苛酷な状況は、知花※※の証言からも窺い知ることができる。軍属であった知花は、部隊から離れた日本兵七人と山中で行動を共にした。そこで知花が見たのは、日本兵と現地の人々の殺し合い、日本兵同士の殺し合いであり、死んだ「仲間」の肉を食べるという状況であった。昭和二十年四月から八月に集中している読谷山村出身者戦没者数は、山中に追い詰められ、食料が尽きた日本兵と日本人移民たちの苛酷な状況を反映しているのではないだろうか。
<-前頁 次頁->

![]()

![]() 、十二月十九日、山下第十四方面軍司令官は、鈴木第三十五軍司令官にレイテ作戦終了を通告した。
、十二月十九日、山下第十四方面軍司令官は、鈴木第三十五軍司令官にレイテ作戦終了を通告した。![]() 。
。![]() 。日本兵や日本人移民たちは山間部への避難を余儀なくされた。その頃、「在留日本人の子どもは作戦上足手まといになるので殺してもよいという命令」が出ていたことや、味方同士で食べ物の奪い合いをするという状況が生じたと城田吉六は述べている
。日本兵や日本人移民たちは山間部への避難を余儀なくされた。その頃、「在留日本人の子どもは作戦上足手まといになるので殺してもよいという命令」が出ていたことや、味方同士で食べ物の奪い合いをするという状況が生じたと城田吉六は述べている![]() 。
。![]() 。
。![]()