<-前頁 次頁->
シベリア抑留への経緯
旧ソ連領であったシベリアは、昭和七年(一九三二)に日本が中国東北部に建国した「満州国」と隣接していた。しかし国境線は不明確なもので、この国境線をめぐり日ソ間は緊張していた。昭和十四年(一九三九)にはノモンハン事件(満州と外蒙古との国境近く、ハルハ川沿岸で起きた日ソ両軍の衝突事件)が起き、関東軍(満州における日本の駐屯軍)はソ連軍から壊滅的な打撃を受けた。村内からもこの年の七月から八月にかけて、ノモンハンで伊良皆の山内※※、楚辺の比嘉※※、比謝の知花※※らが戦死している。
昭和十五年(一九四〇)、日本は「大東亜共栄圏」樹立の構想を打ち出し、南方への武力侵略を強化することにした。この北守南進の態勢を固めるため、昭和十六年(一九四一)四月に日ソ中立条約を結んだ。
昭和十六年(一九四一)六月、日本軍は関東軍特別演習(関特演)を実施し、ソ満国境付近に大軍を動員した。これは陸軍参謀本部の方針で「もし、“極東に動乱勃発、極東兵力の西送、ソ連政権の崩壊”といった情勢が起れば、ソ連領に攻めこむつもりだった」(『太平洋戦争・上』児島襄、一九六五、三頁)からである。
この関特演で召集を受けたのは、波平の比嘉※※のように、現役入隊の経験がない年長者(当時三十二歳)も含まれていた。比嘉は、熊本で一か月間訓練を受け、すぐに満州へ行ったという。この時、比嘉と同じ明治四十二年生まれの知花※※(波平)、知花※※(波平)などが一緒に召集を受け渡満しているが、二人はその後南方に派遣され、フィリピンで戦死している。
当時国境の町、黒河で軍属として働いていた喜名の安里※※は、関東軍国境守備隊が布陣しているのが見えたという。しかしその守備隊が「昭和十九年(一九四四)頃には、南方へ移動して兵舎は空っぽになり、構築した陣地は少人数の兵隊が守っていた」と証言している。また国境付近の虎林にいた渡慶次の玉城※※も同様なことを述べている。
座談会の中で、波平の新垣※※は「現役兵や若い方をどんどん南方の激戦地へ向かわせ、満州に残ったのはほとんど関特演での召集兵であった」と証言している。これは、武力によるシベリア侵略を断念した日本軍が、関東軍主力部隊を次々と南方戦線へ移動させていたからであった。
昭和二十年(一九四五)になると、軍属として満州に渡った玉城※※や安里※※(当時十九歳)が、二十歳を待たずに繰り上げ召集を受け、初年兵として国境周辺に配置された。この時期、新京第一中学校の三年生一三〇名が、東寧報国農場での作業という名目でソ連国境の最前線に送られている(『ソ満国境十五歳の夏』田原和夫著、築地書館、一九九八年刊より)。しかし、このとき日本陸軍は首都新京以南を守る態勢をとっていたため、召集兵、補充兵、及び開拓団が多く残されていたソ満国境付近はすでに放棄されている状況であった。
昭和二十年(一九四五)八月八日、ソ連は日ソ中立条約を破棄し、対日宣戦布告をした。綏芬河(スイフンガ)・黒河・ハイラルなど多方面から国境を越え、約一五〇万人のソ連軍が「満州」に侵入した。これに対抗する関東軍は半数以下の約七〇万人であった。しかも主力部隊を欠き、守備陣地は未完成のうえ、装備も不十分で、戦闘経験のない現地召集兵が一〇万人を占めていた。
この時の戦闘状況について、座談会出席者は皆「ほとんど戦闘らしい戦闘はなかった」と述べている。戦闘開始から一週間後の八月十五日、日本はポツダム宣言を受諾し、無条件降伏をした。日ソ両軍の間で停戦協定が結ばれ、約七〇万人の関東軍は武装解除された。
戦争が終わり、日本兵は祖国の家族の元へ帰れるはずであった。ところが、その後ソ連は軍事捕虜として、約六〇万人の日本人を厳寒のシベリアに抑留した。
村内の抑留体験者の話によると、武装解除後、将兵を始めとする在満日本人はソ連軍に捕まり、中間集結地として新京、ハルビンなどに収容された。その時ソ連兵は「ダモイ・トウキョウ(東京に帰れる)」と言っていたという。これらの地に集結した人々はただちに千人単位の「作業大隊」に編成され、列車に乗せられてソ連各地の収容所に輸送された。この列車の中でも帰国を信じ、バイカル湖をみて「日本海が見える」という人もいたという。
「ソ連における日本人捕虜の生活体験を記録する会」代表(一九九〇年現在)の高橋大造は「抑留・六十万人の四年間」(『アルバム・シベリアの日本人捕虜収容所』朝日新聞社、一九九〇)の中でシベリア連行者の数を「厚生省資料の五十七万人をはるかに超え、七十万人にも達するだろうと推定」している。
![]()
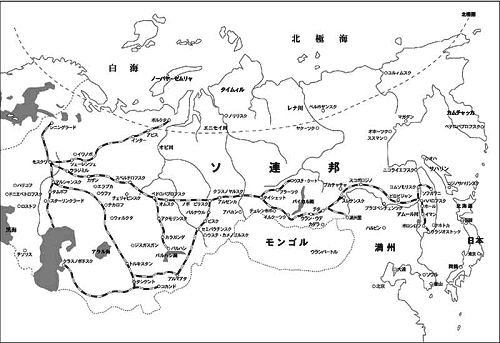
![]()