<-前頁 次頁->
戦前の概況
読谷村の西海岸、残波岬と比謝川河口との間のやや南寄りが都屋海岸で、そこから東に広がる一帯が都屋の地域である。
南は字楚辺に接し、北は波平大当原と境界を一つにする。東は嘉手納製糖工場が敷設したトロッコ軌道を境に本字座喜味との境をなしていた(これは現在も変わらない)。
地域は二分して北の方が都屋大当原、南は都屋原となっており、一般に平地をなしているが、都屋大当原は所々岩の露頭がみられる小丘陵がある。
集落は海岸近くに形成され、戸数は大正八年に字座喜味の内数として二二戸、人口が一二二人となっており(県統計書)、昭和十九年には戸数は五一戸で人口は不明となっている(援護課資料)。
戦前は字座喜味の七組で、俗に都屋組、あるいは屋取(ヤードゥイ)ともいわれ、納税・教育をはじめその他の字行事は本字座喜味と一緒にした。師走御願(シワーシウグヮン)や初御願(ハチウグヮン)には座喜味から(トゥヤーシムン)(取り合わせ物、供出物)として米の徴収に来た。
豊かな海を前にしていることから、明治時代から糸満の漁業者が移住して操業し、やがて伊平屋・伊是名からの漁民もやって来るようになった。
多い時には大小合わせて九つの網元があり、それぞれ雇い子を四、五人から一〇人内外もかかえていた。特筆されることは、二隻の機械船を擁して九州の五島や山口沖まで出漁(ヤマトゥアギヤー)し、さらに現地からの商品も運んで商活動をしたことである。
こうした漁業活動にもかかわらず、漁業組合を設立するのはかなり遅く、昭和十二年一月十日に「保証責任座喜味漁業協同組合」の名で設立し、同年二月十六日那覇区裁判所嘉手納出張所で登記を済ませている。同組合の目的は「漁業権入漁権ヲ取得シ…云々」とあることから、早晩漁業権は取得していたものと推察される(『官報にみる読谷山』より)。
戦時体制下の生活
昭和十二年七月七日、中国蘆溝橋(ろこうきょう)で起こった一発の銃声は駐留日本軍と「支那軍」(中国軍)との衝突となり、やがて「支那事変」(日中戦争)へと発展し、ついに泥沼化の様相を呈してきた。その影響は有形無形に住民の上にのしかかってくる。
配給
昭和十四、五年頃から物資は不足し始め、次第に米は配給制となり、衣料も切符制となる。配給は村(米は食糧営団)から産業組合や漁業組合に物資がきた。都屋では組長の古堅※※の家で配給していたが、その後イリヌミーヤー(店)で配給するようになった。
屠殺禁止
物不足はついに豚や山羊の無断屠殺禁止ということになり、自分の家畜であっても勝手に処分することは許されなかった。それで豚や山羊を屠る時には、あらかじめ監視員をおいて巡査がいないことを見定めてから処理にかかった。とはいえ豚を屠る際は大変な悲鳴をあげるので、棒の先にボロ切れを巻き付け、豚の喉に押し込んで悲鳴があがらないようにした。当時の標語に「山羊は食っても皮は残せ」というのがあった。
訓練
昭和十七、八年頃から浜に出て、区民総出で竹槍訓練や防火訓練をした。訓練の時の指導員は喜名出身の糸数※※だったが、後に応召した。
訓練、警備組織としては、都屋にも支部がおかれ、支部長は古堅※※であった。婦人会も青年団も座喜味に通って連絡を取り合っていたが、婦人たちはモンペに上が襷(たすき)がけであった。また青年たちの役目は主として伝令であった。
訓練空襲警報となると、サイレン等の合図や伝令の通報等があり、灯火管制が行われた。当時は明かりはランプしかなかったが、その上に黒い布や厚紙等をかぶせて光が漏れないようにした。しかしそれはやがて本物の空襲警報に変わり、ほとんど毎晩となった。そうなると灯火管制どころか、ランプを消して暗闇でじっと息を殺していた。
奉仕作業
出征兵士の家の畑仕事の奉仕があり、婦人会や女子青年は米搗(つ)き作業もあった。ナビーメーヒラタの家の後ろで臼三つにそれぞれ二人ずつ付き、計六人で搗いた。
千人針
出征に間に合わせて千人針を作って持たせた。また既に戦地にある兵士に対しても千人針を作って送った。
千人針は、木綿布の腹巻きで、女の人に頼んでそれに一つずつ赤糸の結び目を付けてもらい、千の数に達するようにしたのである。つまり千人の願い、武運長久の心をこめるという縁起物である。通常は一人一つの結び目であるが、寅年の人は年の数だけ結び目を付けることができた。それは虎は一日に千里を駆けるという験(げん)からきたものである。
また千人針の中央部には五銭玉や十銭玉も縫いつけた。五銭は死線を越え、十銭は苦戦を越えるということからきたものである。千人針の唄に「……千人針に真心をこめて私は送るのよ」という歌詞もあった。
祝勝行列
シンガポール陥落(昭和十七年二月)の時、昼は旗行列、夜は提灯行列で祝った。シンガポールは陥落後昭南島と改名された。当時の軍歌では「マライに続くルソン島、快速部隊の進撃に鉄より固き香港も、我が肉弾に砕けたり」と歌った。
出征兵士・見送り
「支那事変」(日中戦争)が勃発するに及んで、都屋からも召集され出征する人が出るようになった。最初に召集されたのは支那事変劈頭(へきとう)の昭和十二年七月の、島袋※※や古堅※※らであった。出征に際しての出立式等は座喜味とは別に行った。字事務所がないので、最初はゴンゴロウモーグヮーで壮途激励会を行ったが、人数が多くなるにつれてアミフシモー(網干し毛)に変わった。
見送りは日の丸小旗を持ち、太鼓を叩いて軍歌を歌いながら応召兵を先頭に歩いていった。その時の軍歌は、露営の歌「勝ってくるぞと勇ましく」とか、出征兵士を送る歌「我が大君に召されたる」等々であった。
トゥンケービラグヮーまで来ると隊列を離れる者もいたが、大方は嘉手納駅まで歩いていった。駅に行くまでには他の字の見送り団体とも合流して大変賑やかになった。
戦死・村葬
都屋での沖縄戦前の戦死者は与儀※※、古堅※※、諸見※※の人々となっている。古堅※※は、新聞で海南島への軍属としての出稼ぎ広告を見て応募したが、現地召集されて蘭印方面(現在のインドネシア)で戦死した。長男※※は長崎での合同慰霊祭に参加し、遺骨を抱いて帰郷した。
古堅※※と牧原の渡嘉敷某が最後の村葬ではなかったかと※※の記憶にある。村葬は忠魂碑の前の道にたくさんの花輪が並んでいて、役場吏員を始め、村内三校区から多くの村民が参列した。
沖縄戦前夜
徴用
戦雲が迫ってくるにしたがい、沖縄でも基地設営が急速に進められていった。その中でも航空基地建設が主となり、北飛行場(現読谷補助飛行場)、中飛行場(現嘉手納基地)、海軍飛行場(現那覇空港)、その他伊江島、西原、石嶺等の飛行場建設に多くの人員と荷馬車等が徴用された。
十五、六歳から四十五、六歳までが徴用の対象で、飛行場から徐々に壕掘り(陣地構築)へと移っていった。遠いところに徴用されると住み込みになった。
徴用に応じない人は普天間まで出頭しなければならなかった。正当な理由がある場合は許された。
棚原※※他漁業従事者は、漁撈(ぎょろう)での徴用ということになっていた。それは都屋駐留の兵隊がそのように計らっていたようである。
ほかにも、※※と石川※※によると、山田(多幸山)の海軍壕掘りに行ったが、落盤事故があり外で待機しているとメーヌミーヤーにいた菊池准尉が通りかかったので、頼んで都屋現場に変えてもらったという。
また、クーニー山の壕掘りに向かっていた古堅※※、阿波根※※らは、十・十空襲で引き返した。
供出
甘藷・黍(マージン)・粟・麦・野菜などの供出物はメーヌミーヤーに集められた。漁業従事者が多いので、魚の供出も多かった。捕ってきた魚は軍のトラックが来て持っていったので、住民は残った小さな魚にしかありつけなかった。また、十・十空襲の時に戦死した兵隊をシナバーマで火葬するため、薪を一束ずつ各戸から供出した。
守備軍の駐屯
守備軍の宿営
昭和十九年の夏頃、守備軍が駐屯してきた。最初にやってきたのは球部隊で、その後山部隊が来た。
山部隊の兵隊は北海道出身者が多く、青森や大阪の人もいた。兵隊は優しい人が多く、住民(彼らは地方人と言った)とは仲がよかった。
大きな家の一番座はほとんど宿舎として提供され、家族はクチャ(裏座)で暮らした。兵員人数は一戸に四、五人いたが、棚原屋は多かった。
| ・ |
メーヌミーヤーには本部があり、駐屯部隊の中心であった。 |
| ・ |
メークシには林准尉がいた。 |
| ・ |
稲福には最初に山部隊の兵隊が四人入ってきた。 |
| ・ |
テーラヤーの門口には初年兵が衛兵として立っていた。 |
| ・ |
阿波根には北海道出身の五十嵐一等兵と亀谷兵長というダイナマイトを扱う技術兵がいた。 |
| ・ |
クシヌミーヤーにもいたが、人数及び部隊名は確認されていない。 |
| ・ |
炊事場として使用されていたのは、稲福、メーヌミーヤー、棚原屋、テーラヤーであった。 |
その後、菊池准尉たちは瀬長に移動することになり、屋号古堅(フルギン)の前で住民たちは見送りをした。
守備軍と住民との関係
最初に稲福に入ってきた兵隊たちに食べさせるために、ご馳走を持っていく人が多かった。「兵隊さんのおかげです」という歌もあったとおり、国土と人民を守ってくれる兵隊さんということで崇めていた。あるいは兵隊への憧れもあっただろう。「ほんとにほんとにご苦労さん」という替え歌も歌われた。
| 一、 |
腰の軍刀にすがりつき 連れていかんせソロモンへ
連れていくのはやすけれど 女は乗せない戦闘機
ほんとにほんとにごくろうさん |
| 二、 |
女乗せない戦闘機なら 長い黒髪切り落とし
軍服姿に身を変えて ついていきますソロモンへ
ほんとにほんとにごくろうさん |
・兵隊は山芋が好きで、時々畑から盗まれることがあった。
降り掛かる戦火
十・十空襲
昭和十九年十月十日の空襲の二、三日前に菊池准尉らが指導しての避難訓練があった。空襲の当日、人々が仕事に取りかかろうとする時、いきなり爆音と爆弾炸裂の轟音が起こった。最初は演習と思い、兵隊たちも急降下急上昇を繰り返す飛行機を見ていた。
実際に敵襲だと分かった時には、避難訓練の指導を守るどころか、慌てふためいてティラの洞窟に逃げ込んだ。空襲は北飛行場を中心に行われていたので都屋には被害はなかった。
相次ぐ事故
本部(もとぶ)から牧港へ薪を運ぶ暁部隊の船がコースを間違えてイナン礁に座礁した。それを米軍機に狙われ機銃掃射されて四人の兵隊が死亡した。
楚辺の浜に靖国号が墜落し、乗員三人の内一人が流れ着いてきた。それを見に行く途中、菊池准尉がハブに咬まれた。
召集(現役兵・防衛隊)
現役兵
新里※※(海軍)、阿波根※※、古堅※※、照屋※※、照屋※※(以上は陸軍壮丁・現地入隊)
防衛隊 (召集年齢と隊員氏名)
十六歳(昭和三年生)から四十四、五歳までの男子に防衛召集が下った。氏名は次の通り
古堅※※、阿波根※※、野波※※、棚原※※、上原※※、島袋※※、島袋※※、又吉※※、又吉※※、喜瀬※※、古堅※※、阿波根※※、古堅※※、新里※※、古堅※※、島袋※※、野波※※
主な軍務内容
防衛隊で、高齢の人は中飛行場構築に当り、若い人は弾薬運び等をさせられた。戦況はかなり悪化していたが、赤紙で召集された。
沖縄に現地召集された人は喜んでいたが、かえって本土に召集された人たちが多く助かったことは皮肉であった。
特志看護婦
古堅※※(現姓※※)は沖縄師範学校女子部本科に在学中看護婦の訓練を受け、昭和二十年三月二十三日から南風原陸軍病院で、いわゆる「ひめゆり学徒隊」の一員として傷病兵の看護に当たった。
沖縄戦末期、守備軍が島尻の南端に追いつめられた頃、「ひめゆり学徒隊」は解散となり、組織を失い、戦火の中に放り出された。
米軍上陸
米軍上陸まで
十・十空襲から米軍上陸までは頻繁に空襲があり、住民はその度ティラの洞窟に避難したが、人命、財産等に被害はなかった。翌二十四日に焼夷弾でカナー古堅が焼けた。
都屋は上陸地
昭和二十年四月一日、米軍はついに都屋からも上陸した。したがって、上陸作戦時の砲爆撃は熾烈を極め、地上物件を完膚なきまでに壊滅させた。上陸と同時に米軍はメーヌミーヤーに野戦病院を設置し、米軍傷病兵を収容し、ティラの洞窟周辺には難民収容所を設けた。
避難
住民が避難した主な洞窟
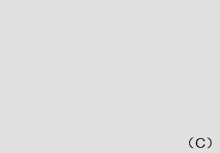 |
| 米軍に収容され都屋の海岸でくつろぐ人々。沖には多数の米軍艦船が見える |
十・十空襲後は空襲の度にティラの洞窟に避難したが、昭和二十年三月二十四日頃、石部隊の兵隊がやってきて作戦のためと称して住民を追い出した。都屋地内ではティラの洞窟の他にメーヌミーヤーの下の洞窟(現在の漁港の下)やマヤーガマ等の洞窟もあった。
波平のシムクガマに避難しようとした人もいたが、そこはすでに波平の人でいっぱいになっており、入れなかった。
老人や幼児をかかえ、その他経済的な理由で村指定の国頭の避難所に行けず、米軍上陸直前に長浜のカンジャーガマに避難した家族もあった。照明弾の明かりをたよりに弾痕を確かめ落ちないように注意しながらようやく長浜にたどり着いた。
避難経路及び避難先
役場から国頭に避難するよう指示があり、避難先も指定されていたが、ほとんどの家族は都屋に残っていた。三月二十四日頃、石部隊による立ち退き命令により、空襲に追われながら国頭方面へ避難を始めた。
避難指定地は国頭村比地・辺土名・奥間であった。西海岸沿いに歩いて三日から一週間もかかった。昼は隠れて、夜になると歩いた。馬車のある家族は積めるだけの生活必需品を積み、そうでないところは持てるだけ持って歩いた。
歩けなくなって座り込む子供もいたし、置き去りにされる老人もいた。着いた頃には、足はぱんぱんに腫れ上がっていた。
指定の避難所に着いてみると、地元の人や先に避難していた人々はすでに山の中に避難した後だった。
山の中では、子供をかかえている家族は嫌がられた。泣き声で敵に知られる恐れがあるというのである。いろいろなデマも飛び交った。「島尻は戦争が終わっているからそこへ突破しよう」とか、「島尻には兵隊がたくさんいて助けてくれる」ということで中部方面へ向かった人もあった。
山の中での地理が分からず、地元の人に金を出して案内を頼んだ。比地あたりで知花清村長と出会った人もいた。
収容所
住民はそれぞれの避難先近くで投降し、その後石川、宜野座、金武、漢那、羽地、仲尾次等々の収容所に収容され、そこで沖縄戦の終わりを迎えた。
故郷への復帰
昭和二十一年(一九四六)の末、読谷山村への移動許可となり、住民は帰村を始めたが波平と高志保の二集落跡地への制限移住を余儀なくされた。しかしこの頃、都屋は座喜味から分離して字を創設した。
昭和二十四年(一九四九)十月、ようやく都屋への移動(移住)が許可され、字民は協力して字再建に乗り出した。(渡久山朝章)
<-前頁 次頁->
![]()
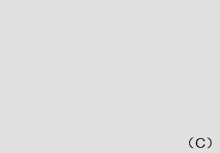
![]()