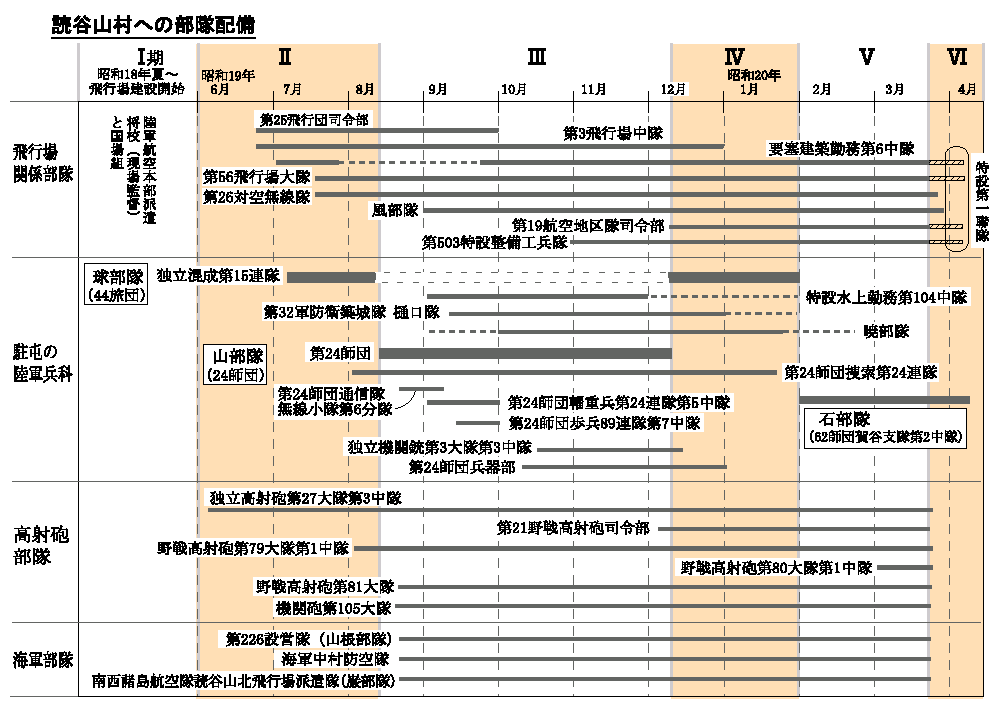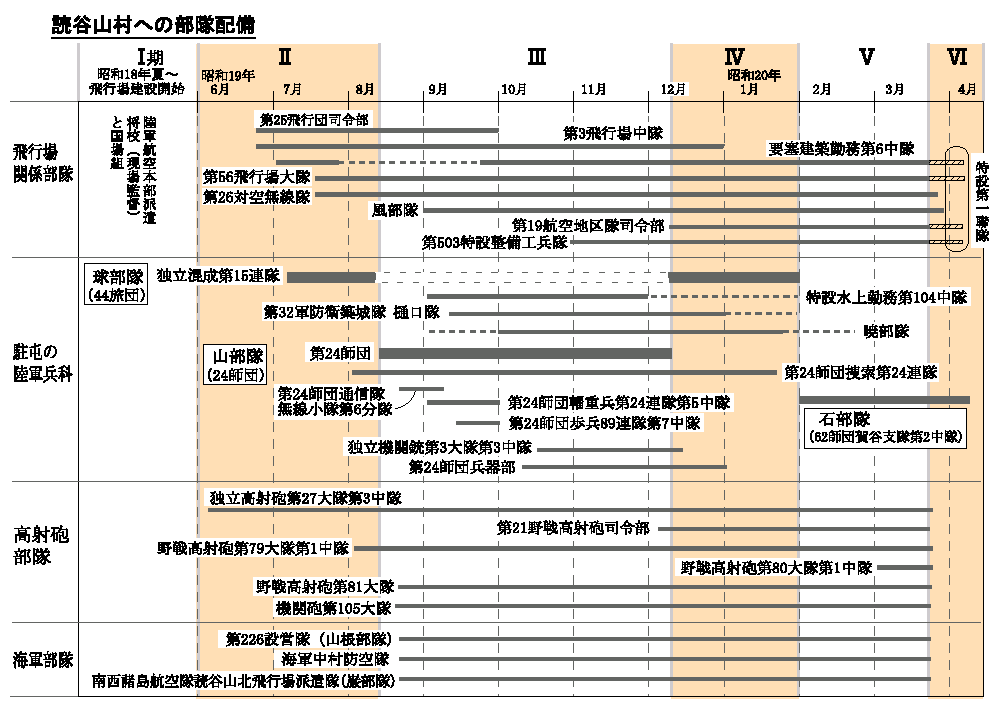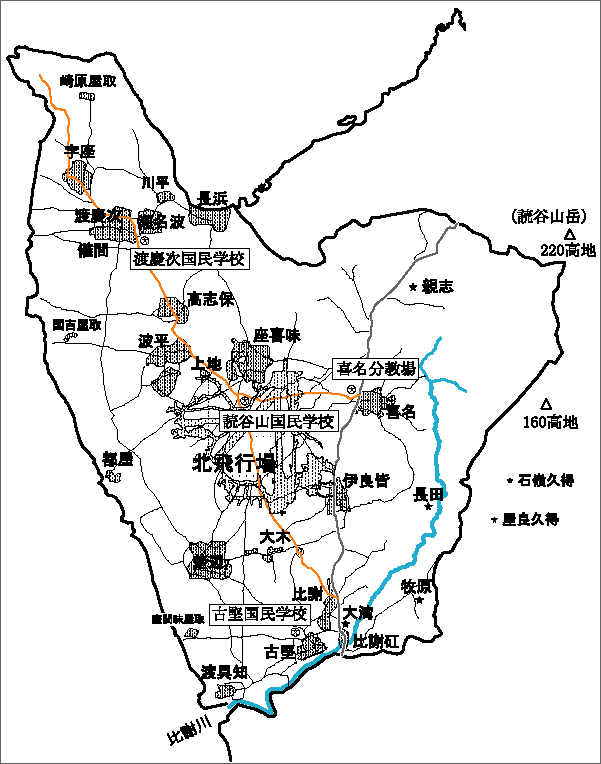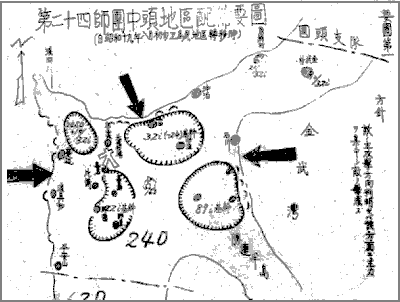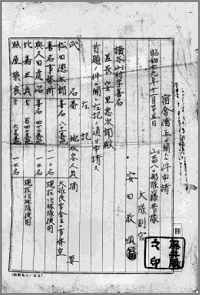第一節 防衛庁関係資料にみる読谷山村と沖縄戦
読谷山村への日本軍部隊配備
4 各部隊について
ここでは、各部隊を大きく五つのグループに整理して記述した。航空地上勤務(飛行場関係)部隊、航空飛行部隊、駐屯の陸軍兵科、高射砲部隊、海軍部隊である。図7は読谷山村への部隊配備を、各部隊ごとに駐屯期間を図示したものである。航空地上勤務部隊及び航空飛行部隊はまとめて飛行場関係部隊に入れた。また期間が不明もしくは曖昧なものに関しては、記載されていないものもある。
航空地上勤務(飛行場関係)部隊
第三飛行場中隊(誠八三四九部隊)
第十九航空地区司令部の命により、昭和十九年六月二十九日から、東(西原・小那覇)飛行場及び南(仲西・城間)飛行場より北飛行場に駐屯し、飛行場周辺誘導路・掩体・燃弾防護施設等構築作業に従事した。命令には「施設作業ニ関シテハ北飛行場設定担任天野少尉ヲ指揮スベシ、但シ航空本部ニ於テ実施ノ作業ト其ノ区別ヲ明瞭ナラシムベシ」とある。昭和二十年一月一日より台湾の第八飛行師団に編入され、その任務は第五十六飛行場大隊に引きつがれた(『第十九航空地区司令部命令会報綴』より)。
要塞建築勤務第六中隊(球二七七四部隊)
昭和十九年七月四日から昭和十九年七月二十四日まで、第六中隊の金丸班が、北飛行場内の各種土木・建築作業に従事し、その後美里村へ移動した。昭和十九年九月二十七日より、第六中隊第二小隊より重信班が北飛行場に派遣され、第五十六飛行場大隊の指揮下で、各種(三角兵舎、入浴場、便所、炊事場、器材庫、給油補給台、慰安所造りの他、排水溝、発電機、机、戸棚、寝台など)の建設作業、洞窟壕掘り等に従事した。昭和二十年二月十九日より、本隊とともに第十九航空地区隊の指揮下に入り、昭和二十年三月二十三日、特設第一聯隊編成にともない同聯隊第二大隊(中飛行場)に配属された(「陣中日誌」沖縄戦資料75、77、78より)。
第五十六飛行場大隊(球九一七三部隊)
昭和十九年七月二十二日、沖縄本島へ上陸し、第十九航空地区隊司令部指揮下にて北飛行場に駐屯した。大隊本部、補給中隊、警備中隊からなり、南方戦線へ向かう飛行部隊への燃料補給、事故機の処理、対空監視、給与が主任務であるが、燃料弾薬集積所や掩体壕、誘導路造りなどの飛行場建築作業や、米軍機の来襲に備え、器材を洞窟へ格納したり、駐留飛行機を掩体壕に収容するなど、飛行場各施設全般の遮蔽、偽装も任務とした。昭和二十年三月二十三日、特設第一聯隊編成にともない同聯隊に配属された(「陣中日誌」行動の概要 昭和十九年十二月・「戦闘詳報」より)。
図7
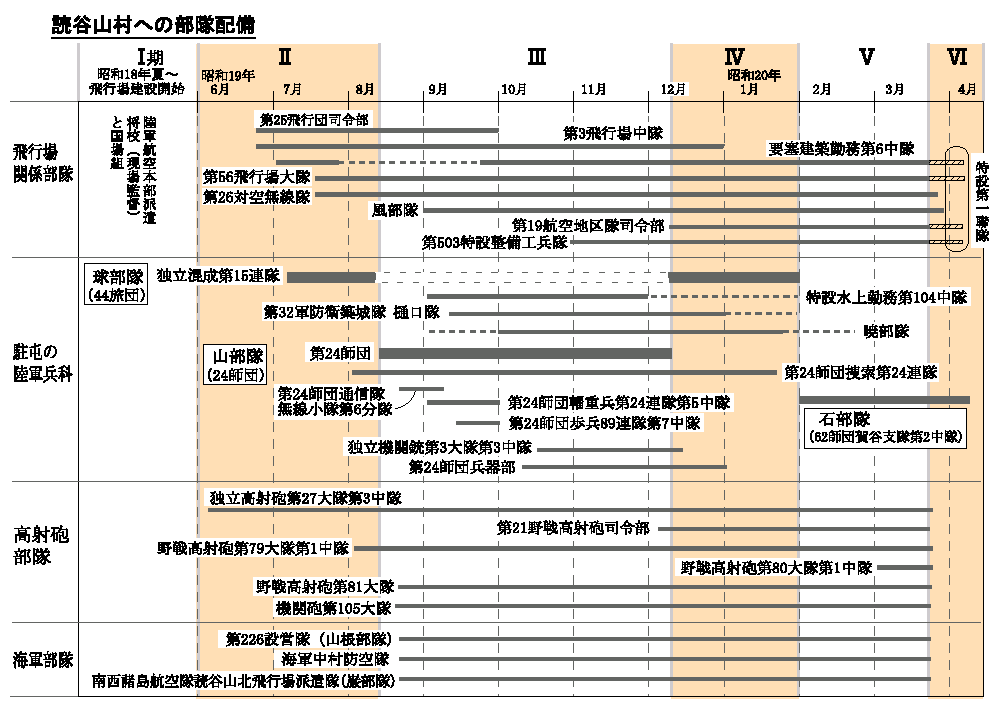
|
第二十六対空無線隊(誠一六六二六部隊)
昭和十九年七月、「満州」の関東軍隷下から台湾第八飛行師団に入り、主力は沖縄本島へ移動した。七月二十二日那覇港に上陸し、本部と主力は北飛行場に配備され、知覧、徳之島、伊江島、中飛行場(嘉手納)、小禄、宮古島、台湾台北の各飛行場に無線分隊を派遣し、第二十五飛行団指揮下の飛行部隊の南西諸島交通保護作戦に協力した。その他南西諸島通過並びに往来する飛行部隊の空地通信に関し協力するほか、飛行場の整備や同付属施設工事に従事した。
昭和二十年三月下旬、第三十二軍命令により第六十二師団(石部隊)の指揮下に入り、首里へ移転した。昭和二十年三月二十八日の夕方、「読谷山飛行場に在る喜那(ママ)の宿営地(三角小屋)及通信所並に器材を自らの手で破壊焼却し、軍司令部のある首里方面」へ移動した。
(『在沖縄 第二十六対空無線隊部隊歴史』より)
風部隊
風部隊は、中央航空路部(風一八九一八部隊)と第五野戦航空修理廠第一支廠(湾一九〇二三部隊・大刀洗航空廠那覇分廠より改名)の二部隊から成る。前者は飛行機との通信を主な任務とし、後者は飛行場を離発着する飛行機の輸送関係、燃料補給、整備などを任務としていた。これら二つの部隊は、一九四四年(昭和十九)九月には共に小禄飛行場から北飛行場に移駐し、九月十五日より二つの部隊長を近藤卓二中佐が兼任する兄弟部隊となった。
十・十空襲以前は、伊良皆(現国道五八号西側)に駐屯していたが、空襲後、中央航空路部(保安部)は五八号東側の伊良皆亀地橋付近へ、那覇分廠は比謝深迫原の壕へ移動した。現在もこれら二つの部隊の移転先に、部隊が使用していた壕が残っている。中央航空路部の第五保安中隊の渡辺泰次中隊長の「風部隊始末」によると、昭和十九年九月一日夕方に読谷山村北飛行場に到着し、十・十空襲の翌日より北飛行場東方約二キロの山中の三角兵舎に入り、洞窟通信所の建設にかかったが、その際地元民の協力(一日平均一五人)を求め、作業力は一日一メートル平均であったと記されている(『風一八九一八部隊沖部隊中城隊(第五保安中隊)覚書』所収より要約)。
昭和二十年三月下旬、第六十二師団の指揮下に入り、風部隊は首里へ移転した。軍属としてこの部隊と行動を共にして、戦死した読谷山村民は約五〇人に上る。
(「陣中日誌」、『航風 創刊号』風部隊之碑管理団体航風会発行より)
第十九航空地区隊司令部(球二五六九部隊)
昭和十九年四月十五日、第三十二軍司令部より沖縄本島及び伊江島の航空基地設定を命じられる。同月二十五日より北飛行場設定は、第十九航空地区隊司令部の指揮下に置かれ、従来の航空本部管轄、国場組請負いの工事と区分が分担された。
昭和十九年十二月十一日から昭和二十年三月まで読谷山村大湾に駐屯し、北飛行場建設関係部隊を指揮した。昭和二十年三月二十三日、特設第一聯隊編成にともない同聯隊に配属され、第十九航空地区司令官であった青柳時香中佐が特設第一聯隊の聯隊長となった。
誠第一整備中隊
第十九航空地区隊司令部指揮下にて北飛行場に駐屯。昭和二十年三月二十日以降、第二十一航空通信隊隷下に入る。三月二十三日、特設第一聯隊編成にともない同聯隊に配属された(『第十九航空地区司令部命令会報綴』より)。
第二十一航空通信隊(誠一九一五九部隊)
第十九航空地区隊司令部指揮下にて昭和二十年三月二十日に編成され、北飛行場へ配備された。隷下部隊は第二十六対空無線隊残置隊、誠第一整備中隊であったが、三月下旬、軍命により第六十二師団の指揮下に入り首里へ移転した(『第十九航空地区司令部命令会報綴』より)。
西部軍情報隊城隊
一九四四年(昭和十九)七月十三日より、北飛行場付近に展開した。第二十五飛行団に協力し、対空警戒を任務とした(『沖縄・臺湾・硫黄島方面 陸軍航空作戦』より)。
第三十二軍航空情報隊安武隊(球一九五六四部隊)
第三十二軍航空情報隊は、昭和十九年七月四日編入の独立第一・第二警戒隊などを含んで、昭和二十年二月十三日に編成された。安武隊は、二二〇高地(読谷山岳)にて野戦用警戒機によって米軍機の行動や戦闘状況を偵察し、那覇警戒本部へ報告(昭和二十年一月三日の報告例あり)することを任務としていた。高射砲司令部の「戦闘要報」に「軍情報連隊安武隊(二二〇高地)の警戒機の目標捕捉およびこれが情報の伝達極めて適確にして、高射部隊の戦闘準備に寄与するところ大なり」と記されている(昭和二十年一月二十二日)。
図8
当時の読谷山村。各学校敷地や各字事務所、村東方山岳地帯を中心として、各部隊が駐屯していた。
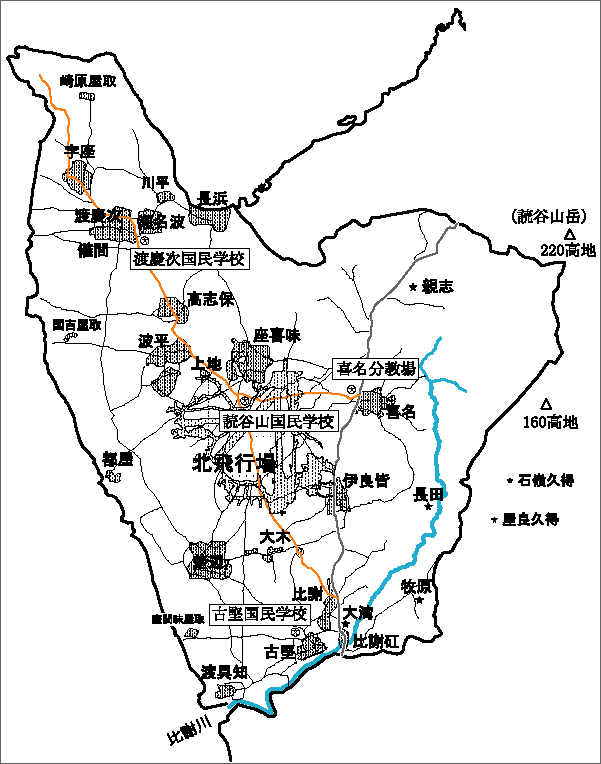
|
第三十二軍防衛築城隊樋口隊(球一六一六部隊)
第三十二軍の増加要員で関東軍築城部より臨時に編成され、通称号も第三十二軍司令部と同じである。昭和十九年八月二十五日那覇へ上陸し、八月二十九日より中飛行場にて築城工事を開始する。九月十日より北飛行場において戦闘機入掩体(アーチ形)工事に従事、沖縄県人勤労隊が協力した。昭和十九年十二月十二日、首里へ移動した(史実資料二「沖縄戦資料62」より)。
特設第一聯隊
昭和二十年三月二十三日、第一大隊(北飛行場)および第二大隊(中飛行場)で編成された。第一大隊の任務は、主力をもって二二〇高地の既設陣地に拠って努めて長く北飛行場を制扼することなどであった。
特設第一聯隊長 青柳時香中佐
聯隊本部(第十九航空地区司令部) 約四五人
第一大隊長 第五十六飛行場大隊長 黒澤巌少佐
第五十六飛行場大隊 約三七〇人
第五〇三特設警備工兵隊 約八〇〇人
第二大隊長 第四十四飛行場大隊長 野崎眞一大尉
第四十四飛行場大隊 約三九〇人
第五〇四特設警備工兵隊 約八〇〇人
要塞建築勤務第六中隊 約三〇〇人
誠第一整備隊
生徒隊(尚謙少尉の指揮する県立農林学校生徒隊一七〇人)
第五〇三特設警備工兵隊(球一八八一七部隊)
「沖縄戦当時の部隊所在表」(防衛研修所戦史室)によると、一九四五年三月三十一日現在で第五〇三特設警備工兵隊(球一八八一七部隊)は、本部、第一中隊、第四中隊が古堅におかれ、第二中隊が伊良皆、第三中隊が座喜味に配備されていた。この部隊は防衛隊によって編成された部隊であり、「防衛召集概況一覧表」(防衛研修所戦史室)によると以下の通り、県下各地から防衛召集を受けている。小禄(一五〇人)、豊見城(一三〇人)、南風原(八〇人)、真和志(一〇〇人)、首里(二〇〇人)、那覇(二〇〇人)、浦添(一〇〇人)、宜野湾(一〇〇人)、羽地(五〇人)。召集の時期は、一九四四年(昭和十九)十月下旬と一九四五年(昭和二十)二月中旬である。四月一日頃、読谷山村から越来村白川付近に向かい、再び石川岳に転進したとある。
読谷山村民への防衛召集は、隣接する北谷村(現嘉手納町)に駐屯していた第五〇四特設警備工兵隊(球一八八一八部隊)に、一九四五年二月十日一五〇人が召集を受けた。
航空飛行部隊
第二十五飛行団司令部
ビルマ方面への移動準備中であった第二十五飛行団は、一九四四年(昭和十九)六月二十六日、台湾の第八飛行師団(空中戦闘部隊)に編入され、沖縄に展開することになった。第二十五飛行団司令部(団長福沢丈夫中佐)と二個飛行戦隊(飛行第三戦隊・飛行第二十戦隊)が北飛行場に配備された。任務は、南西諸島の近海(鹿児島以南、石垣・台湾基隆の線以北)における防空、敵潜水艦の攻撃から日本艦船の航行安全を守ることであった。
北飛行場を根拠飛行場とした第二十五飛行団は、九月三十日に台湾に移動した。
飛行第三戦隊
第二十五飛行団の隷下で、一九四四年(昭和十九)六月二十七日頃より北飛行場に配備され、同飛行場を根拠地とした。同年九月下旬に台湾へ移動したが、一部の整備隊員は米軍上陸まで読谷山村楚辺に駐屯していた(『沖縄・臺湾・硫黄島方面 陸軍航空作戦』より)。
飛行第二十戦隊
第二十五飛行団の隷下で、一九四四年(昭和十九)六月二十七日頃より北飛行場に展開して船団援護に任じていたが、同年八月下旬に主力が小港、一部は台北へ移動して台湾南部の防空に任じた(『沖縄・臺湾・硫黄島方面 陸軍航空作戦』より)。
独立飛行第二十三中隊
一九四四年(昭和十九)十月十日の大空襲に際し北飛行場に位置し、中隊長以下一〇機で敵を遊撃した。十・十空襲時、沖縄方面に配備されていた唯一の戦闘飛行部隊であった(『沖縄・臺湾・硫黄島方面 陸軍航空作戦』より)。
飛行第六十七戦隊
第二十五飛行団隷下の部隊で、一九四四年(昭和十九)六月二十六日より、徳之島を根拠飛行場としていた。史実調査参考資料報告「沖縄戦資料8」には昭和二十年「四月一日、北飛行場、四月四日屋嘉ニテ戦闘」と記されている。
駐屯の陸軍兵科
独立混成第十五連隊(球部隊)
昭和十九年七月八日、読谷山村に独立混成第四十四旅団指揮下の独立混成第十五連隊(球七八三六部隊)が配備された。「陣中日誌」を要約すると、連隊本部は古堅国民学校、第二大隊本部は喜名・伊良皆・座喜味、第五中隊は喜名、第四中隊は喜名国民学校、第六中隊は波平字事務所、第二機関銃中隊は読谷国民学校、連隊砲中隊は古堅、工兵中隊は古堅国民学校、神谷小隊は渡慶次にそれぞれ駐屯した。八月初旬までの約一か月間の駐屯後、北部方面へ移動した。
昭和十九年十二月から昭和二十年一月末までの一か月間、再び独立混成第十五連隊が読谷山村へ戻ってきた。第二大隊、第四中隊、第六中隊、第二機関銃中隊は渡慶次に駐屯した。ところが、独立混成第十五連隊は度重なる配備変更により、昭和二十年一月下旬に知念方面へ移動した。
第二十四師団(山部隊)
山部隊は一九三九年(昭和十四)末以来、「満州」で国境警備に当っていたが、昭和十九年七月十四日第三十二軍に編入された。八月五〜七日に沖縄本島へ到着し、その一部は十二月初旬まで読谷山村に配備された。その間九月下旬には、軍命令により師団主力が北飛行場造りに投入された。第二十四師団(山部隊)指揮下の駐屯部隊は、以下の通りである(図9参照)。
歩兵第二十二連隊(山三四七四部隊)は屋良久得に本部が置かれ、読谷山村には比謝矼から牧原、長田にかけて駐屯した。歩兵第三十二連隊(山三四七五部隊)は司令部が恩納村の山田国民学校におかれたが、一部は読谷山にも駐屯した。捜索第二十四連隊(山三四七八部隊)は、親志、座喜味、長浜辺りの山地(ウトゥンガー)に駐屯した。独立機関銃第三大隊第三中隊(球六〇九〇部隊)は、九月二十八日より第三十二軍命令にて第二十四師団に配属され、十月十五日より十二月初旬まで、捜索第二十四連隊の配下で座喜味において陣地構築作業に従事した。
輜重兵第二十四連隊(山三四八三部隊)は喜名付近に駐屯し、自動車大隊は古堅国民学校に配備された。防疫給水部(山一二〇七部隊)は喜名付近に駐屯し、臨時野戦病院を開設した。ハンセン病患者の収容も任務としていた。
第二十四師団通信隊無線小隊第六分隊(山三四八二部隊)は、昭和十九年八月五日渡具知港より上陸後、嘉手納農林学校に駐屯していたが、昭和十九年八月二十三日から昭和十九年九月四日まで、喜名一六〇高地に駐屯した(九月五日以後国頭村安波に配備)。
野砲兵第四十二連隊(山三四八〇部隊)は石嶺久得に駐屯し、二二〇高地で陣地構築に従事していたが、九月下旬北飛行場完成に向けて建設作業に従事した(図10参照)。歩兵第八十九連隊第七中隊(山三四七六部隊)も九月十八日から九月二十九日まで、親志の弾薬・燃料集積所、道路構築等、北飛行場周辺の築城作業のため配備された。第二十四師団兵器部(山三四八四部隊)は、十月十一日から十二月まで一六〇高地に駐屯した。
これらの山部隊については、古堅校にはトラックが五〇台余り置かれていたことや、村内の山から材木の切り出しをしていたこと、北海道出身兵が多かったことなどが当時の村民の記憶に残っている。
昭和十九年十二月、第九師団(武部隊)の台湾移転に伴い、第二十四師団(山部隊)は南部方面に移動した。
図9「第二十四師団中頭地区配備要図」
(自昭和十九年八月初旬至島尻地区移転時)
『沖縄戦資料1』所収「第二十四師団沖縄作戦記録」(第二十四師団生存者に依り終戦後留守業務部に於て作成されたるもの) より注:iは歩兵連隊、SOは捜索連隊の部隊記号
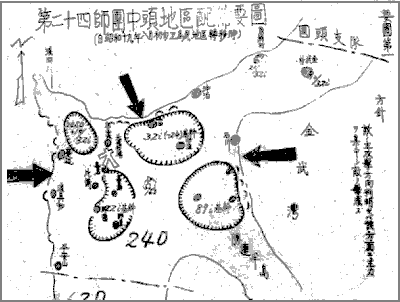
|
図10
「宿舎借上ニ関スル件申請」山三四八〇部隊昭和十九年十一月二十五日
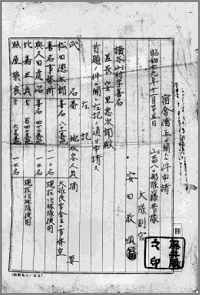
|
暁部隊
船舶部隊の通称。沖縄本島に配備されたのは、第五海上挺進基地隊本部指揮下の各海上挺進基地大隊(一〜三、二十六〜二十九大隊)、及び第七野戦船舶廠第一支廠(第七船舶輸送司令部沖縄支部の要員を基幹として昭和十九年十一月十日編成)、及び船舶通信隊である。船舶の輸送業務に従事するこの部隊が比謝川沿いに配備され、昭和十九年秋頃から昭和二十年一月頃まで駐屯していた。船舶からの軍用物資の陸揚げは、特設水上勤務第一〇四中隊の朝鮮人軍夫があたっていた。一九四五年二月以降、主力部隊は独立歩兵隊に改編された。
特設水上勤務第一〇四中隊(球八八八七部隊)
沖縄第四十九兵站地区隊嘉手納支部の指揮下にて、昭和十九年九月一日より読谷山村字渡具知に露営し、比謝川河口の陸揚場にて、軍用物資の陸揚げ・搭載・運搬、また嘉手納駅にて物資の積み卸し、ならびに道路工事、陣地構築等に従事した。約五〇〇人の朝鮮人軍夫が作業にあたっていた。十月には本部(もとぶ)地区へ、十一月には那覇へも派遣されているが、残ったものは渡具知で継続して陸揚げや陣地構築に従事した。
第六十二師団独立歩兵第十二大隊第二中隊(石部隊賀谷支隊)
昭和二十年二月より、第六十二師団から賀谷支隊(独立歩兵第十二大隊・石三五九三部隊)第二中隊が派遣された。第二中隊の主力を石嶺久得付近に配備し、読谷山村には、第一小隊が座喜味西方海岸(国吉屋取)に、第二小隊が座喜味東方高地へと、二つの小隊が配備された。任務は「中頭郡内の警戒に任ずると共に所在軍直部隊と協同し、同方面の防備が厳重なように敵を欺騙(ぎへん)する」(注8)こと、つまり戦闘ではなく、敵である米軍を騙して誘導することであった。
米軍上陸と共に、特設第一連隊の青柳連隊長の指揮下に入り、昭和二十年四月二日南部へ向かったが、宇久田付近で米軍と遭遇し多大な死傷者を出した。
高射砲部隊
独立高射砲第二十七大隊第三中隊(球一二五一七部隊)
独立高射砲第二十七大隊は、昭和十九年六月十日那覇に上陸し、大隊本部・第一中隊(ガジャンビラ)、第二中隊(天久)は那覇上空の防衛のための陣地構築作業にあたり、第三中隊は読谷山村座喜味に配備された。第三中隊の任務は北飛行場の守備であり、陣地構築には嘉手納にあった沖縄県立農林学校の生徒が動員された。昭和二十年三月二十二日第三中隊は南部へ移動となり、座喜味にあった六門の高射砲は、具志へ四門、小渡へ一門、国吉へ一門移転された。
野戦高射砲第七十九大隊(球二一七二部隊)
野戦高射砲第七十九大隊は、昭和十九年八月十日に大隊本部、第一中隊が、八月二十三日に第二中隊、第三中隊が那覇に到着し、それぞれ読谷山村に駐屯した。任務は北飛行場の守備であった。第一中隊は、昭和二十年三月二十六日まで座喜味(石根原(イシンニーバル)から尾頓川(ウトゥンガー))に駐屯したが、第二、第三中隊は、昭和十九年十月にはそれぞれ那覇、国頭の防衛の任についた。第一中隊が読谷山を撤退した昭和二十年三月下旬には、大隊全てが那覇、島尻地区の戦闘につき、六月には斬り込みを敢行し部隊は壊滅した。
野戦高射砲第八十一大隊(球一二四二五部隊)
第二十一野戦高射砲司令部指揮下で、昭和十九年八月二十日から昭和二十年三月下旬まで北飛行場周辺に駐屯した。連隊本部は伊良皆、第一中隊は大木、第二中隊は楚辺、第三中隊は伊良皆にそれぞれ駐屯し、北飛行場の防空任務についた。『沖縄の最後』で第一中隊に所属していた著者古川成美は、石灰岩台地での陣地構築作業で「土を掘り、岩をえぐる。シャベルとつるはしだけの熱汗作業。(中略)中隊六門の火砲を地中に隠すその陣地を掘り下げる」苦闘の中「風土になれぬうえに、荒仕事にもなれぬひ弱な兵士は次々と病いに倒れた」と記載している。
昭和二十年三月六日、村内から島尻方面へ防衛召集を受けた人達が「役場で一日講習を受けた後、夕方、現読谷高校グラウンドにあった野戦高射砲第八十一大隊で夕飯を取ったが大変おいしかった」と証言している。昭和二十年三月二十七日、第六十二師団に配属され南部へ移動。昭和二十年五月十日、首里に転進。戦闘が激しくなるにつれて真栄平、真壁へと移り、同年六月十九日、残存兵力大隊長以下約一五〇名が斬り込みを敢行し、部隊は壊滅した。
機関砲第一〇五大隊(球一二四二六部隊)
昭和十九年八月二十一日には、楚辺赤犬子原に機関砲第一〇五大隊が配備された。その後、第二十一野戦高射砲司令部指揮下にて、昭和二十年三月二十三日まで北飛行場南側、楚辺などに駐屯した。
機関砲第一〇三大隊(球二一七七部隊)
第二十一野戦高射砲司令部指揮下にて、波の上周辺海岸地区の守備についていたが、防衛庁沖縄戦資料「高射部隊対空戦闘詳報」昭和二十年一月四日の高射部隊配置図より、一部北飛行場東側に配置されていたことが確認できる。
第二十一野戦高射砲司令部(球一二五四五部隊)
第二十一野戦高射砲隊司令部は、第九師団指揮下にて本島所在の高射砲大隊を指揮し、那覇泊付近に配備されていた。第九師団(武部隊)の台湾移転に伴い、主力は昭和十九年十二月六日から北・中飛行場に移転し守備についた。武部隊や山部隊に配属されていた高射砲部隊などの全てを、軍高射砲隊として第二十一野戦高射砲司令部が統一指揮することになり、その司令部は大湾の字事務所に配置された。指揮下の部隊は独立高射砲第二十七大隊、野戦高射砲第七十九大隊、野戦高射砲第八十大隊、野戦高射砲第八十一大隊、機関砲第一〇三大隊、機関砲第一〇四大隊、機関砲第一〇五大隊、海軍中村防空隊(『沖縄方面陸軍作戦』より)であった。
野戦高射砲第八十大隊第一中隊(球二一七三部隊)
第二十一野戦高射砲司令部指揮下にて、昭和二十年三月三日から三月二十四日まで、高射砲二門をもって読谷山村字高志保の国吉屋取に駐屯した。本部、第二中隊、第三中隊は中飛行場(嘉手納)守備についた。
海軍部隊
南西諸島航空隊読谷山北飛行場派遣隊(巌部隊)
昭和十九年八月下旬より昭和二十年三月末まで北飛行場に六〇〇人が配備された。本部は小禄飛行場に駐屯しており、総兵力二八〇〇人であった(『八月十五日の天気図』矢崎好夫著より)。「南西諸島海軍航空隊戦時日誌」によると昭和十九年八月十三日「沖縄北基地整備開始」とあり、九月半ばには北飛行場に海軍航空機「銀河」が一三機と記録されている。十月十日の空襲では「銀河」一〇機が炎上、三機が未帰還と記されている。
海軍中村防空隊
海軍陸戦隊。第二十一野戦高射砲司令部指揮下にて、北飛行場北側の守備にあたる。防衛庁沖縄戦資料84「高射部隊対空戦闘詳報」内の高射部隊配置図などに記載がある。
第二二六設営隊(山根部隊)
沖縄方面根拠地隊大田實司令官指揮下の設営隊で、隊長は山根巌少佐であった。昭和十九年八月末から昭和二十年三月下旬まで駐屯していた。第二二六設営隊は小禄飛行場に配備されていたが、副長以下九〇人余が北飛行場へ派遣された(『沖縄方面海軍作戦』より)。
【コラム】海軍部隊への徴用 伊禮※※(当時十四歳)沖縄市在住
十九年八月の末ごろ、喜名観音堂に駐屯していた海軍の中村隊に、徴用されることになった。中村隊は来たばかりで、テントが四張りぐらいしかなかった。海軍のテントは白い色でイカリマークが付いていた。この隊には高射機関砲があり、一基から銃身が上下に二本出ていたと思うが、六基ほどあった。一基に二名の兵隊が付いていた。敵機が来たらこの機関銃を撃てるように、見張りの兵二人がいつも立っていた。中村隊長はよくいらして、双眼鏡で対空監視をしていた。私たちは兵隊が宿泊するテントを張るための地ならしをしたり、川の水を一時貯める池のようなものもつくらされた。
観音堂の入口辺りに一メートルくらいの高さの杭に、墨で「海軍中村隊」と書かれた立て札が打ち付けられていた。宿舎は喜名の国民学校で、コの字型の校舎の向かって左奥には、海軍山根部隊がいました。飯場は真ん中にあり、右と左は陸軍が使っていた。徴用人夫は入口付近に宿泊だったが、入りきれなくなったので私たちは民家に宿泊した。喜名の屋号※※という姓だったが、その立派な家は、私たち徴用人夫に占領されてしまって、おじいさんはクチャグヮー(裏座)で、おばあさんは炊事場で休まれていました。朝は七時出勤、夜も暗くなってしか帰れませんでした。
喜名観音堂から、今度は親志の弾薬壕掘り、燃料壕掘りに回された。燃料壕は一〇箇所くらい、名護に向かって道路左側に掘られていた。近くに陸軍の軍人倶楽部(慰安所)があった。
穴を掘ると、そこに高さ二メートルくらいに切られた琉球松の丸太を枠にはめていた。丸太をカスガイでとめて、鳥居のような形にして、それを壕に入れていた。兵隊は壕に来て巻尺を持ってきて計ったりして、指示を出していた。私がいた頃には燃料庫は一〇箇所以上掘っていたようだ。アメリカ製のつるはしや、青や赤のペンキの塗られた柄の長いスコップなどを使っていたのが珍しかった。海外での分捕り品だったんではないかな。
喜名の国民学校で、山根部隊の隊長だったのか、みんなを集めて作業前に訓示があった。敵はサイパン島もテニアン島も攻撃して、次は沖縄だから、一分一秒でも早く完成させよ、と言っていました。この朝の訓示のときは、校庭いっぱいの徴用人夫だった。山根設営隊の隊長は那覇勤めらしく、主に副隊長がここをみて、隊長は週に一回ぐらい見回りに来たのではないかと思う。
昭和二十年三月末までは居て、あとは自然解散だった。
(調査者玉城栄祐、藤本愛美 二〇〇三年)