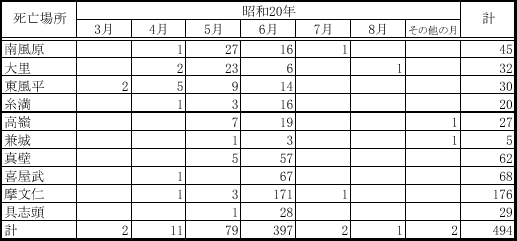第四節 「読谷村戦没者名簿」からみた戦没状況
二 県内での戦没状況
前掲〔表2〕の県内での読谷山村民戦没者数の内訳は〔表7〕のようになる。
沖縄県内での読谷山村民戦没者数は、二〇〇二年三月現在判明している分で二九四七人である。沖縄で地上戦が行われた一九四五年(昭和二十)がもっとも多く二七〇一人となっている。これを年・月別にみたのが〔図2〕である
戦没者数は一九四五年(昭和二十)四月から六月にかけてもっとも多く一九三三人にのぼり、県内での戦没者総数二九四七人の五七%にあたる。
昭和十九年の戦没者は十月十日のいわゆる十・十空襲に集中している。昭和十九年十月十日に陸軍所属の軍属六四人が久米島沖南方海上で戦死したほか、読谷山村で二五人、那覇で六人、沖縄から八重山へ向かう船上で一人、計九六人の戦没が記録されている。
昭和二十年を地域別に見ると、以下の地域で戦没者が多い。

米軍上陸前、読谷山村住民の疎開指定地となった国頭村をはじめ、その他沖縄本島中南部地区の住民の疎開指定地であった大宜味村、東村、久志村、羽地村の北部地域で七〇九人

米軍上陸後、読谷山村民の多くが収容された金武・宜野座地域で二六三人

石川収容所のある美里村で一四〇人

地元読谷山村で四七七人

中部戦線の激戦地、浦添村・西原村・首里市で二六八人

南部の南風原村で四五人、大里村・東風平村で六二人、糸満町、高嶺村、兼城村、真壁村、喜屋武村、摩文仁村、具志頭村一帯で三八七人
以下に地域別に見た読谷山村民の戦没状況をまとめてみた。
 北部地域での戦没状況
北部地域での戦没状況
北部地域で戦争の犠牲となった読谷山村民の数(昭和十九年〜昭和二十一年)は次のようになる。
北部地域は米軍上陸前の住民の疎開指定地域であった。一九四五年二月十日、沖縄本島中南部地区の住民三九万人に対して北部地区への疎開が決定された。当初一〇万人を移す計画だったが、実際には約三万人が疎開したといわれている。北部地域一帯で一九四五年(昭和二十)に戦没した読谷山村民の数は七〇九人にのぼっており、米軍の上陸地点となった地元読谷山村での同年の戦争犠牲者四七七人をはるかに超えている。
『東村史』によると北部各町村への疎開民の割りあては、次のようになっていた。
・国頭村(読谷山村・浦添村・真和志村・那覇市)
・大宜味村(那覇市・真和志村)
・東村(具志川村・読谷山村)
・久志村(中城村・西原村・佐敷村)
・金武村(東風平村)
・羽地村(美里村・越来村)
・名護町(小禄村)
・今帰仁村(宜野湾村・伊江村)
(『東村史』より)
読谷山村に対しては六三九〇人の疎開割りあてがあり、『読谷村誌』(昭和四十四年発行)には「国頭村奥間部落に読谷山村仮村役場をおいて此処を中心として比地・桃原・辺土名・伊地・与那あたりまで部落単位の集団避難を実施し」たとある。実際に何人が避難したのかは明らかになっていないが、仲宗根源和著『沖縄から琉球へ』(一九七三年発行)には、一九四五年(昭和二十)十月調査の「辺土名市居住外来者分布状況調査表」〔表9〕が掲載されており、当時の読谷山村民の居住状況が把握できる。北部地域(ヤンバル)での避難生活は米軍の北部への進攻(四月十二日頃)後も続けられ、大部分の人が山中生活を終えて米軍収容所(辺土名地区、田井等地区、瀬嵩地区)に収容されるのは七月中旬頃といわれる。これらの収容地区のうち辺土名地区での居住状況が〔表9〕となる。一九四五年十月はすでに各収容地区からの帰村がはじまる時期にあたるが、その時点で一四〇五人の読谷山村民が北部の「辺土名市」に居住していた。読谷山村以外の各市町村からの居住外来者の合計は三六九七人である。
〔表9〕辺土名市居住外来者分布(1945年10月)
米軍は七月に国頭山地の全面的な掃討作戦を実施することを宣言し、七月十五日が下山の期限であったという。宣言通り十五日ごろから全面的な掃討作戦が展開され、現在の福地ダム方面から次々に山林が焼き払われ、夜は照明弾を打ちあげて空陸から敗残兵の捜索が行われた。十七日ごろには猛火は県道近くまで迫り、火炎放射器で焼き払われた家屋も少なくなかったという。「七月に入るや、度々の下山勧告に応じないのにしびれをきらした米軍は、隊を編成して山中に分け入ってきた。そうして要所要所に立哨し、勧告と探索を続けて、日本軍の斬込隊を捕まえるとともに住民を収容して無事に下山せしめようと努めるようになった」(『地方自治七周年記念誌』一九五五年発行より)。
米軍上陸後、すでに五月、六月頃には食糧が底をつき、山中で避難生活を続ける住民は飢えとたたかいながら山中をさまよった。その結果、収容先は辺土名地区、瀬嵩地区、久志地区、田井等地区と分散することになった。昭和二十年二月から十二月まで(一月は〇人)の戦没者数およびその死亡原因は〔表10〕および〔表11〕のようになる。
米軍によって設定された収容地区との関連でみると、国頭・大宜味・東は辺土名地区に、久志は瀬嵩地区に、羽地は田井等地区にほぼ相当する。四月から七月にかけて戦没者が多いが、収容所での死亡とみられるものは少なく(後半になると多くなる)、大部分は収容前の山中での避難生活中の死亡とみられるものである。死亡原因別では「栄養失調」が圧倒的に多く三七三人に及んでおり、ヤンバルでの避難生活の厳しさを表している。米軍の北部進攻後の四月から、大部分の人が収容所に収容される七月まで、山中をさまよい飢えに倒れていった様子を表している。「爆撃他による死亡」の一三五人に対して、栄養失調、マラリアを含む「病死」は四七五人に及んでいる。
〔図3〕は昭和二十年二月〜十二月までの北部地域での戦没状況をグラフ化したものである。
北部地域での戦没者数(昭和20年2月〜12月)〔表10〕
 金武・宜野座地区での戦没状況
金武・宜野座地区での戦没状況
金武・宜野座では総数で二九八人の読谷山村民が死亡している。昭和十九年から二十一年までの戦没者数は〔表12〕のようになる。戦争が終結し、収容地区からの帰村がすでにはじまっている一九四六年(昭和二十一)にも二〇人の死亡者がでているのは、読谷山村への帰村が大幅に遅れ、金武・宜野座の収容地区(漢那地区・宜野座地区・古知屋地区)に多くの読谷山村民が残されたためである。ちなみに「読谷村戦災実態調査」より帰村前の居住地を調べると、判明した一万一〇四三人の約三二%にあたる三五三三人が金武・宜野座の収容地区(漢那地区、宜野座地区、古知屋地区)から帰村していることがわかった。その全体の内訳は〔図4〕に示されるようになる。もっとも多いのは次に述べる石川地区である。
昭和二十年二月から十二月までの金武・宜野座地区での読谷山村民の戦没状況は〔表13〕および〔図5〕のようになる。
月日を特定できない「不明」が六〇人にものぼるというのも、金武・宜野座地区の収容所での混乱した状況を示しているといえるだろう。米軍上陸の四月に二三人、中部地域で激戦が続く五月に四八人、牛島司令官の自決によって日本軍の組織的抵抗が終結したとされる六月に三七人、しかしその後の七月に三二人、八月に二九人と戦争犠牲者の数は依然として多い。一九四五年(昭和二十)九月にはいってはじめて戦争犠牲者の数は急減する。戦火もようやくおさまり、八月には「沖縄諮詢会」が創設され、九月末には沖縄本島全域で市会議員選挙・市長選挙が行われた。これによって沖縄本島一二の収容地区は一二の市として一応の行政機構が備わり、犠牲者の急減につながったのであろう。
読谷村戦没者数・金武・宜野座地区(昭和20年)〔表13〕
 石川収容所での戦没状況
石川収容所での戦没状況
米軍の上陸地点となった読谷山村では、一部の地域を除いて住民居住が許されず石川地区へ収容された人が多い。米軍は四月三日には美里村内の石川を避難民収容地区に指定した。『石川市史』は「米軍は石川を避難民収容所となし、読谷、北谷方面その他の避難民を続々と収容し始めた。(途中省略)一番多いのは那覇、読谷、北谷方面の人であった」と記している。「読谷村戦災実態調査」によると、村内楚辺に四月二日頃設けられた臨時住民収容所から次第に石川へ移動させられた住民も多い。また北部地域へ避難した人びとも、いったんは北部地域の辺土名地区や瀬嵩地区、久志地区などに収容されるが、やがて移動が自由になると読谷に近い石川地区や金武・宜野座地区へと移動してくる。前掲〔図4〕「帰村前の居住地」にみるように石川地区から読谷山村へ帰村する住民が圧倒的に多く、五七九五人にのぼる。
石川地区のある美里村での戦没者は総数で一七五人にのぼるが、うち戦闘によると思われる「爆撃他による死亡」が二七人(場所は不特定)記録されており、その「死亡年月日」は昭和二十年三月から六月にわたっている。その他の一四八人の戦没状況は〔表14〕のようになる。
一九四四年(昭和十九)の四人はいずれも十二月頃の戦没である。一四八人中一四六人は「一般住民」とあり、死亡原因も「病死・栄養失調」が圧倒的に多い。大部分は収容所で亡くなったものと思われる。一九四六年(昭和二十一)にも二七人もの人が病死その他で亡くなっているのは、金武・宜野座地区とも共通しており、帰村できずに収容先で亡くなったものである。
石川に収容所ができる一九四五年(昭和二十)四月以後を月別にみると〔表15〕のようになる。
一九四五年(昭和二十)一月から三月までは総数で六人であるのに対して、四月以後は毎月十人前後の人が「病死・栄養失調」で亡くなっている。
 地元読谷山村での戦没状況
地元読谷山村での戦没状況
読谷山村への米軍による攻撃は、一九四四年(昭和十九)十月十日のいわゆる十・十空襲、一九四五年(昭和二十)一月三・四日の空襲、一月二十一・二十二日の空襲、三月一日の空襲があり、三月二十三日からはずっと空襲が続いた。また三月二十六日頃からは艦砲射撃もはじまっている。そして四月一日読谷山村楚辺・渡具知海岸から米軍は上陸した。
「読谷村戦没者名簿」にみる村内での戦争犠牲者は総数で五二八人にのぼるが、月別にみると〔表16〕および〔図6〕のようになる。一九四四年(昭和十九)十月の項目は、いわゆる十・十空襲での犠牲者二五人を含む。米軍が上陸した一九四五年(昭和二十)四月が圧倒的に多く犠牲者の数は三六三人にのぼっている。
読谷山村では、一九四五年(昭和二十)二月三日から国頭への避難が始まっており、三月二十三日から米軍による空襲が毎日のように続くなかで北部ヤンバルへの避難も多くなる。村内に残った人たちは自宅壕や近くの壕へ避難しているが、二十六日頃からは艦砲射撃も加わり被害を大きくした。この艦砲射撃による被害をもっとも直接に受けたのが宇座の人びとで、西海岸に面した海岸沿いの自然壕「ヤーガー」でのできごとだった。「読谷村戦没者名簿」に記録された宇座での戦没者は計三一人にのぼるが、『残波の里(宇座誌)』(一九七四年発行)には、激しい重爆撃と艦砲射撃が続くなかでついに三月二十九日、ヤーガーの入り口近くに砲弾が射ち込まれるという「ヤーガーの悲劇」が起こったことが記されている。「部落に残っていた殆どの人々が、ヤーガーに避難していた。(途中省略)一瞬にして三十一名の人が爆撃の犠牲になってしまった」(『残波の里(宇座誌)』より、また『読谷村史・第五巻・戦時記録上巻』「各字の沖縄戦・宇座」参照)。「読谷村戦没者名簿」の記録では宇座での戦争犠牲者は三月二十九日二二人、三月二十八日一人、三月二十三日四人、残り四人の日付は特定が困難であるが、いずれもほとんどは「ヤーガー」での戦没である。調査では(特に調査の時点で戦後四十年を経過した)特定困難な日付のばらつきはあるが、「ヤーガーの悲劇」は米軍上陸がせまって艦砲射撃と爆撃が激しくなるなかでの読谷山村で最初の大きな悲劇であった。米国陸軍省編『沖縄―日米最後の戦闘』には次のように記されている。「日本軍は、渡具知海岸への水路一帯に、強力な機雷を敷設してあった。したがって、米軍はその掃海作戦が完了するまでは、うかつに海岸近くには寄れなかったのだ。しかし、三月二十九日の夕方になって、はじめて渡具知海岸へつづく広大な面積にわたって行なわれた、ブランディ提督のいう『前代未聞の大掃海作戦』の結果、接近できたのである。三月二十六日から二十八日までの艦砲射撃は遠距離で、しかも視界も悪かったため目標もつかめず効果も少なかった。(途中省略)米軍の艦砲射撃が十分に威力を発揮できるようになったのは、戦艦、巡洋艦、砲艦が、ぐっと島に近づいてそれぞれ目標をきめて、しだいに効果をあげるような艦砲射撃をやりだした三月二十九日からである。(途中省略)艦砲射撃は海岸に望む断崖絶壁を狙って激しく撃ち込まれた」。宇座のヤーガーはまさに「海岸に望む」地にあった。
米軍上陸がせまる三月末から上陸直後の村内での戦没状況は〔図7〕に示されるようになる。
三月二十七日は北飛行場のある座喜味で七人、高志保で三人、いずれも「爆撃」によって死亡しており、渡具知、古堅では「艦砲」によって二人が死亡。二十八日は渡具知で「艦砲」によって一人死亡。二十九日は二二人が宇座で死亡(内一八人はヤーガーで「艦砲」による死亡と記録されている)、渡具知で三人が死亡している。ここまでの戦争犠牲者はいずれも上陸地点に近い海岸線および米軍の上陸目標といえる日本軍の北飛行場周辺に多い。
四月一日は米軍上陸の日であるが、村内で九五人の戦争犠牲者がでた。内訳は波平で三〇人、座喜味で一九人、楚辺で九人、比謝矼および比謝川上流で一九人、喜名および伊良皆の山中で七人がそれぞれ戦争の犠牲となっている。
四月二日には犠牲者はさらに増えて一二六人にのぼる。内訳はチビチリガマでの「集団自決」が八一人(※チビチリガマ碑での「集団自決」刻銘者の数は八五名である)、楚辺で五人、村内で多くの人が避難した喜名、伊良皆の山中では一七人が犠牲となっている。伊良皆のクーニー山では二人の「自決」が記録されている。
四月二日には村内海岸線の都屋、楚辺に臨時の住民収容所が設けられ米軍による住民の保護がはじまっている一方で、三日以後の犠牲者は喜名および伊良皆の山中に集中している。三日には三二人、四日は三人、五日は一八人がそれぞれ喜名・伊良皆・長田に広がる山中で戦没している。喜名・伊良皆・長田にまたがる山岳壕の周辺では、昭和二十年四月の戦争犠牲者は九三人にのぼり、内一三人は「自決」と記録されている。「クーニー山壕」(喜名・伊良皆・長田)での「自決」に関しては、『証言沖縄戦』(琉球新報社発行)に詳しい証言記録が掲載されている。
村内都屋、楚辺に設けられた臨時住民収容所は、石川地区や金武・宜野座地区に設定された本格的な収容所へ移動となり廃止されているから、四月七日以後の村内での戦争犠牲者は五五人にとどまった。
村内での戦没状況を死亡場所別にまとめたのが〔表17〕である。一九四六年(昭和二十一)と一九四七年(昭和二十二)の項目に波平と高志保のみが記録されているのは、読谷山村への住民の帰住が認められたのがこの両地区のみだったからである。『村治十五年』(読谷村役所発行一九六二年)によれば、「一九四六年八月十二日村長知花英康氏は六百の建設隊を引き連れて郷土読谷山に乗り込んだ。見渡す限りの軍施設で元の読谷山はその面影さえも止めないほどの変わりかたであった。而も居住許可地域は僅かに波平高志保の一部分に限られているのでどう手をつけてよいか分からない状態であった。(途中省略)第一回の受入が一九四六年十一月二十日に開始された。第一回受入は十二月十二日一応完了した。この一次の移動によって約五〇〇〇人の村民が懐かしい郷里読谷に帰ったわけであるが、住民地区として許可になっている所は二十二ヶ部落の中、僅かに波平の一部と高志保の一部であったので高志保以北各区民は高志保に、波平区以南の各区民は波平区に混成雑居し、逐次各区の開放を待つという状況であった」とある。
 中部戦線(浦添・西原・首里)での戦没状況
中部戦線(浦添・西原・首里)での戦没状況
一九四五年(昭和二十)四月一日読谷山村海岸線から上陸した米軍は、四月三日には泡瀬方面まで進攻、四月五日嘉数高地付近に達している。四月十九日日本軍守備軍本部のある首里の総攻撃を命令した米軍は、四月二十二日には第二四師団を首里攻防戦に投入、五月四日日本軍守備軍も総反撃に出た。こうして日本軍第三十二軍指令部が首里撤退を決定する五月二十二日まで、首里攻防をめぐって激戦が続いた。五月三十一日には米軍が首里を占領している。
この間に中部戦線で犠牲になったと思われるのが、〔表18〕にあげる中部戦線(浦添、西原、首里)での戦没者である。
〔表18〕の昭和二十年の戦没者二六八人のほとんどは、米軍と日本軍との間で激しい攻防戦が行われた四月から五月にかけて戦死している〔表19〕。
読谷村戦没者数・中部戦線(昭和20年4月〜6月)〔表19〕
 南部地域での戦没状況
南部地域での戦没状況
沖縄戦最後の戦場となった南部地域では、戦闘は次のような経過をたどる。牛島司令官が南部へ向けて首里を撤退したのが五月二十七日、その後米軍は六月七日には小禄の中心部まで進出しており、小禄に本部を置く海軍沖縄根拠地隊との激しい戦闘の末、六月十三日海軍首脳が壕内で自決。六月十五日には南部の八重瀬岳陥落、六月十六日与座岳陥落、六月十七日国吉方面丘陵陥落と続き、六月二十三日牛島司令官が自決して日本軍の組織的な戦闘は終わりを告げる。
南部地域での読谷山村民の戦没状況は〔表20〕のようになる。すべて一九四五年(昭和二十)の戦死で四九四人に及ぶ。昭和二十年を月別にみると〔表21〕のようになる。
五月に七九人、六月に三九七人の戦死者が出ており、七月になるとその数は激減してわずかに二名を数えるのみとなっている。
七月、八月にも多くの戦争犠牲者が出ている北部地域の住民避難地および金武・宜野座の住民収容地域とは対照的な結果となっている。


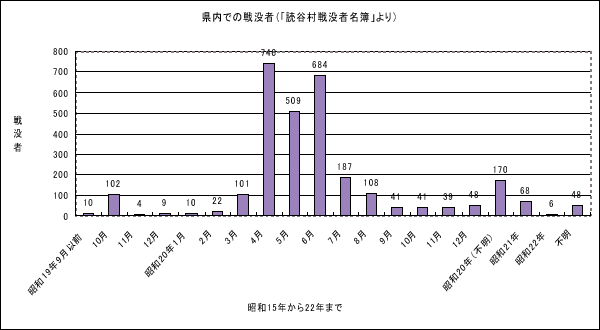
 米軍上陸前、読谷山村住民の疎開指定地となった国頭村をはじめ、その他沖縄本島中南部地区の住民の疎開指定地であった大宜味村、東村、久志村、羽地村の北部地域で七〇九人
米軍上陸前、読谷山村住民の疎開指定地となった国頭村をはじめ、その他沖縄本島中南部地区の住民の疎開指定地であった大宜味村、東村、久志村、羽地村の北部地域で七〇九人
 米軍上陸後、読谷山村民の多くが収容された金武・宜野座地域で二六三人
米軍上陸後、読谷山村民の多くが収容された金武・宜野座地域で二六三人
 石川収容所のある美里村で一四〇人
石川収容所のある美里村で一四〇人
 地元読谷山村で四七七人
地元読谷山村で四七七人
 中部戦線の激戦地、浦添村・西原村・首里市で二六八人
中部戦線の激戦地、浦添村・西原村・首里市で二六八人
 南部の南風原村で四五人、大里村・東風平村で六二人、糸満町、高嶺村、兼城村、真壁村、喜屋武村、摩文仁村、具志頭村一帯で三八七人
南部の南風原村で四五人、大里村・東風平村で六二人、糸満町、高嶺村、兼城村、真壁村、喜屋武村、摩文仁村、具志頭村一帯で三八七人
 北部地域での戦没状況
北部地域での戦没状況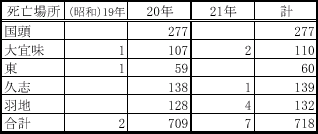



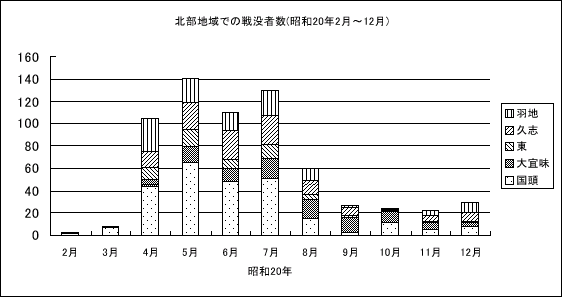
 金武・宜野座地区での戦没状況
金武・宜野座地区での戦没状況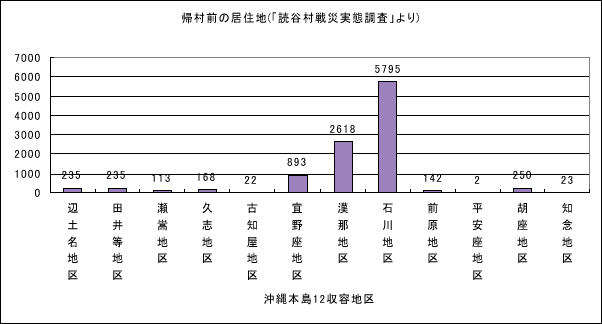
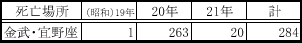
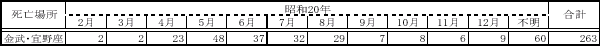
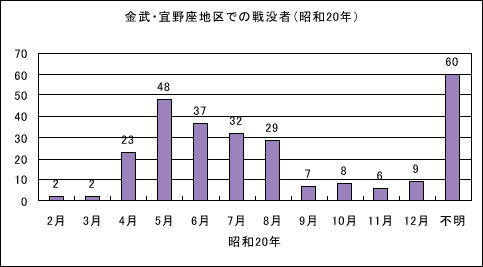
 石川収容所での戦没状況
石川収容所での戦没状況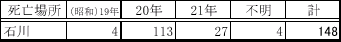

 地元読谷山村での戦没状況
地元読谷山村での戦没状況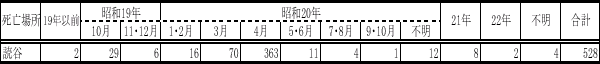
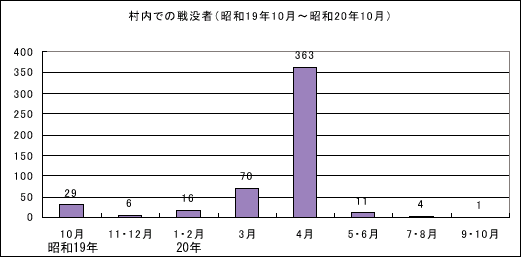
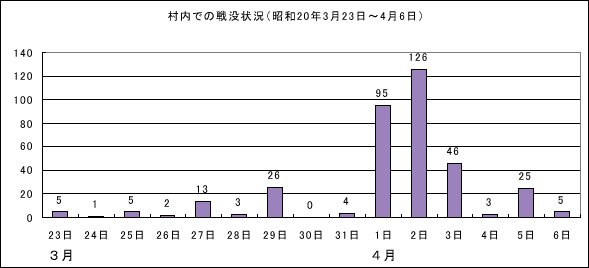
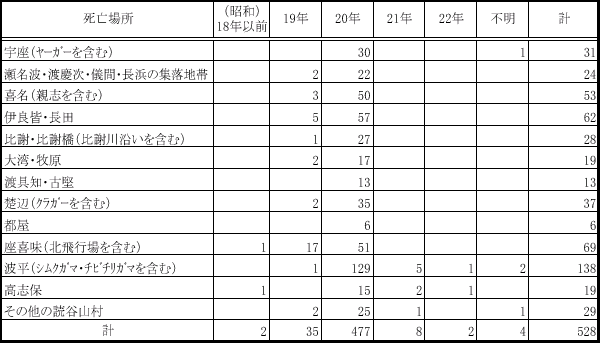
 中部戦線(浦添・西原・首里)での戦没状況
中部戦線(浦添・西原・首里)での戦没状況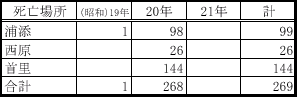
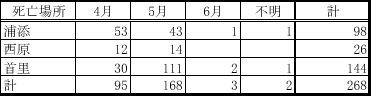
 南部地域での戦没状況
南部地域での戦没状況