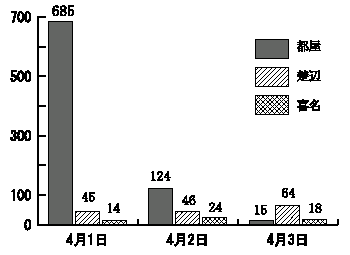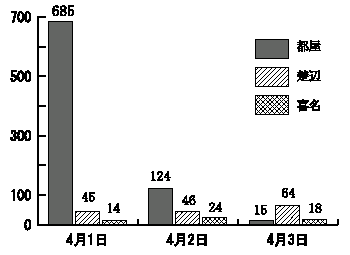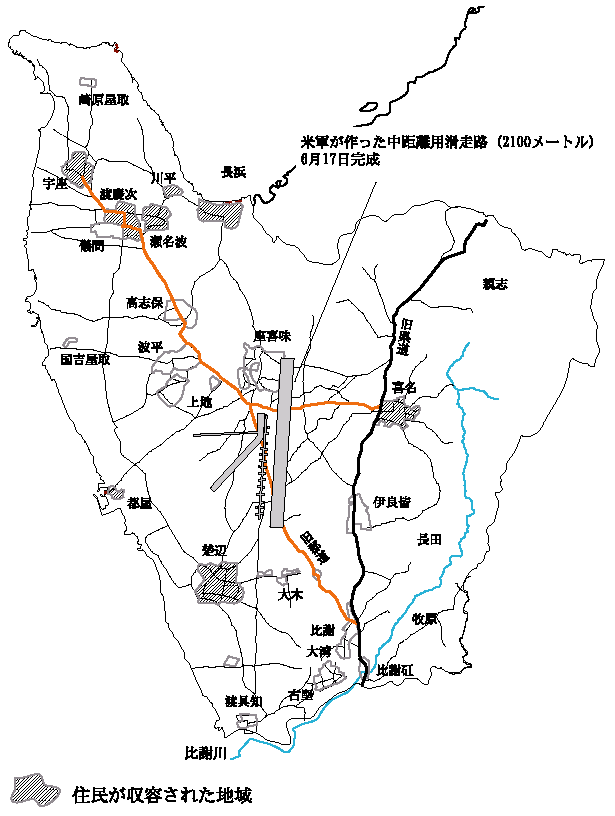第四章 米軍上陸後の収容所
二 読谷山村内での臨時住民収容
一九四五年四月一日、読谷山村渡具知の海岸より上陸した米第六海兵師団は、同日読谷山村都屋に臨時住民収容所を設置、多数の村民を収容した。その数は「戦災実態調査」で判明している分だけで六八五人になる。都屋には最も多くの村民が一時収容され、日付不明も含めた都屋収容者の総数は一三七一人であるが、四月十日前後には閉鎖された。四月一日には、楚辺集落や喜名の役場跡にも村民が収容され、四月一日から三日までのこの三か所での収容者数は左図「村内での収容者数」のようになる。これは日にちが判明している分だけの統計だが、日にちの記載がない分も含めると、この三か所での総数は一八二五人になる。読谷山村全体での収容者の総数は二〇三二人であるから、大部分はこの三か所での収容ということになる。米軍資料には、楚辺には一二軒の家屋しか残っていなかったため、一〇〇〇人の住民がその家屋を使用したと記されている(『沖縄県史 琉球列島の軍政』四八頁)。
村内での収容者数(4月1日〜3日)
「戦災実態調査」より作成
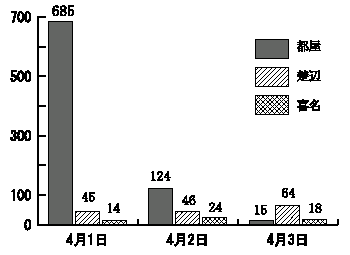
|
米軍は、上陸後わずか数時間を経た午前十一時過ぎには北(読谷)飛行場を占領したが、上陸の翌日にあった読谷山村内での戦闘の様子を次のように記している。
上陸の翌日、第六海兵師団は読谷の下方に進撃をつづけ、渡具知の浜の北西部の半島を偵察して、海岸沿いの村落長浜を占領した。山岳地帯のこの辺では、踏みならされた小径が、森や稜線を縫ってクモの巣のように走り、洞窟や珊瑚礁岩や険しい谷間のいたるところにあった。この山脈の稜線や洞窟に立てこもって、日本軍は頑強な抵抗ぶりをみせた。第六海兵師団はこの頑強な陣地を攻撃し、二陣地を殲滅して、日本軍およそ二五〇名を殺した。時に四月二日。(米国陸軍省編『沖縄 日米最後の戦闘』光人社発行、九五頁)
この日本軍は喜名東の山にいた第五十六飛行場大隊、通称球九一七三部隊(隊長黒澤巌少佐)をさすと思われる。部隊は石兵団派遣の一個小隊約三〇〇人と住民で編成された防衛隊三〇〇人、さらに本田主計大尉を長とする一〇〇人余で構成され、当時座喜味のトーガー壕から喜名東の山の壕に移動していた。隊長以下全員が壕から突撃して、壕の前の田んぼは五〇〇人余の死体で埋まったと『喜名誌』(一九九八年発行)には記されている。後に喜名区民の手でこれらの遺骨が収集され、梯梧の塔が建立され、また部隊の生き残りの人たちの手によって山吹の碑が建立されている。同じ四月二日には、米第六海兵観測隊が北(読谷)飛行場の使用を開始している(なお戦闘部隊の使用開始は三日から)。
四月一日から六日にかけての住民の犠牲も相当の数にのぼる。
「読谷村戦没者名簿」に記された読谷山村内での死亡者数は、四月一日に九五人、二日一二六人、三日四六人、四日三人、五日二五人、六日五人である。このうちには「自決」と記されたものもかなり含まれ、一日に楚辺クラガーで「入水自決」八人、波平で一四人、長田で二人、二日には波平のチビチリガマで八二人(実数八三)の「集団自決」、伊良皆のクーニー山壕で三人、三日には伊良皆クーニー山壕で四人、また五日にも伊良皆クーニー山壕で一人、六日には波平自宅壕で二人の「自決」が記されている。四月一日から六日までの「自決」は一一六人にのぼるがその後読谷山村内での「自決」の記録はない。米軍にとっては「無血上陸」といわれたが、読谷山村内ではこれだけの住民が犠牲を強いられた。
四月五日には読谷山村比謝に米海軍軍政府を樹立、ニミッツ布告を発して軍政に着手した。
読谷山村内での住民収容地区
集落は参謀本部陸地測量部作成の5万分の1地形図(大正10年測図)を元にした
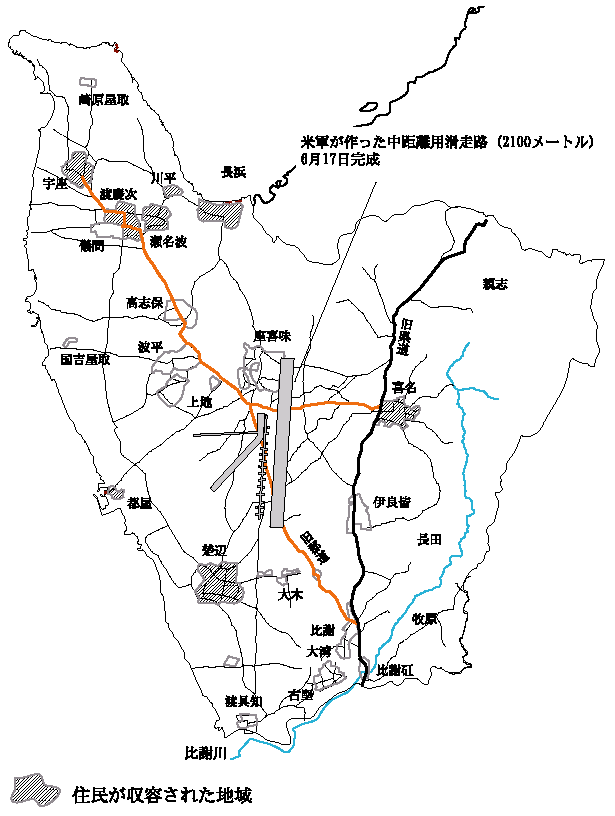
|
収容された住民の移動
読谷山村内に収容された二〇三二人の当初の収容先は、すでに記したように都屋、楚辺、喜名の三か所がその主なものであったが、いずれも一時的なもので、その後村内での住民の収容は、読谷山北方の瀬名波、渡慶次、長浜、宇座等に移動している(前頁地図参照)。
この頃渡具知一帯の海岸線は米軍の荷揚げ集積場になっており、また読谷山沖合いに停泊した米艦船および北飛行場を目標にした日本軍による特攻、航空攻撃も頻繁にあった。特に四月六、七日の総攻撃(日本軍の作戦名は「菊水一号」)は、総攻撃機数六九九機、うち特攻機数三五五機という大規模なもので、米軍の被害も沈没八隻、損傷一五隻にのぼっている(本書一八五〜一八六頁参照)。この時期の特攻について『日米最後の戦闘』には次のように記されている。
日本機の定期的な大空襲は、四月中、ずっと継続して行われた。彼らは、日中は、第五八機動部隊や警備艦隊、それに陸上の対空砲火のおよばない距離にある船団をねらって襲撃してきたが、夜になると輸送船団は敵機が近づくと煙幕を張ってかくれたので、読谷、嘉手納両飛行場を主に攻撃し、つぎに渡具知の浜の米軍を攻撃した。(米国陸軍省編『沖縄 日米最後の戦闘』光人社発行、一二二頁)
日本軍の特攻攻撃「菊水作戦」は六月二十一、二十二日の「菊水十号」まで続いた。このような状況下で、都屋収容所はほぼ四月十日前後に閉鎖され、楚辺も四月下旬までに住民の強制移動が行われた。
都屋、楚辺、喜名からの移動は、村内の瀬名波、渡慶次、長浜、宇座のほかに、村外の民間人収容地区、越来村嘉間良や室川、美里村石川、金武村金武、中川、漢那などへの移動が多い。読谷山村内に収容された住民も、五月から六月にかけて全員村外への強制移動となった。
米軍使役として徴発
当初楚辺に収容された住民が強制移動となった後、楚辺には県内各収容地区から集められた沖縄出身の男性(労務者)約五〇〇人が米軍使役として徴発されている。彼らは北(読谷)飛行場の整備等にも従事させられたようである。五月初旬に収容され、七月になると県内の各収容地区に解放されたというから、当初の住民収容とちょうど入れ違いで収容されたことになる。
そのうちの一人真壁※※(楚辺出身)は次のように記している。
羽地の収容所に着いてから三日目の五月一日午前十時頃、約五〇〇人の人たちが集められた。トラックに乗せられたが、車を降りたところは、なんと自分の生まれ故郷である楚辺のクラガーの上の広場であった。
楚辺に着いた五〇〇人余りの男性たちは、各自部落内の焼け残りの家屋で一晩を過ごすことになった。翌日は全員クラガーの上の広場に集められて、各班を編成し宿泊する場所が割り当てられた。宿泊場所は《具屋》、《前々宇座小》、《上地》の三戸が指定された。《具屋》は瓦葺きの家、メーヌヤー、アサギとすべて残っていたので、約二〇〇人の人たちが入ることになり、私もその一人であった。《前々宇座小》は中央にあったので、米兵の宿舎として土嚢(どのう)を積み金網を張り巡らして、五〇〇人余の捕虜を監視していた。
宿泊が決まった翌日からは軍の作業が開始されたが、私が初めて行った作業場はたしか北谷村国直近隣であったと思う。そこでの仕事は、電気用具の運搬作業であった。作業場は毎日ちがう場所で、北飛行場内へ土嚢(どのう)運搬や防空壕構築の作業にも行った。作業を終えて収容所に戻るのが、午後五時から六時頃で、その時は現場からいろいろな物を持ち帰ることができた。
六月頃だと思うが、五、六人のものが兵隊の事務所に呼び出され、明日から各班の班長になり、清掃や班の世話をし、割り当てられた人員を出して軍の要求に応ずるようにと通達された。
七月四日になって五〇〇人全員広場に集められたが、その頃は沖縄南部戦線で日本軍が敗退し、米兵たちは大変やさしくなっていた。そして作業員を三回に分けて、家族の住んでいる地域に移動させるとのことである。二か月間の楚辺での捕虜生活に別れを告げ、家族の元へ行けるということは、もう私たち全員の喜びであった。
七月五日にはいよいよ出発ということになり、広場に集められて一〇台のトラックに各班毎に分乗し、田井等の収容所に戻された。(『楚辺誌 戦争編』一二四〜一二七頁より抄録)
また比嘉※※(楚辺出身)も楚辺に収容された一人で、次のように記している。
私が捕虜になった頃には、最初に楚辺に収容されていた捕虜はすでに石川収容所に移されていた。そして辺土名、羽地、伊江村などの収容所から集められた労務者や、捕虜になった日本兵が、クラガーの上(《登殿内》の畑)や《前宇座》、《前々宇座小》、《大喜名》などの屋敷にテントを張って収容されていた。一般住民(労務者)はMG、兵隊はPWで表していた。六時起床で八時には仕事に就き、食事は当番制で兵隊も一緒だった。楚辺出身者も二〇人ほどいた。その後七月頃に石川収容所に移されたが、そこからまたさらに八月末頃に宜野座に移され、そこで家族と再会することができた。(同書二一三頁)
この時期の楚辺での収容は、前述した一般住民の収容とは別のもので、時期的には一般住民が村外の住民居住区へ強制移動となった後の収容であり、また後述する日本兵を収容した「楚辺捕虜収容所」とも別のものである。